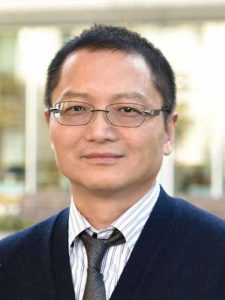専門家レビュー
中井徳太郎 | 周牧之 | 安斎隆 | 大西隆 | 武内和彦 | 横山禎徳 | 南川秀樹 | 森本章倫 | 楊偉民 | 陳亜軍 | 徐 林 | 周其仁 | 李 昕 | 張仲梁
気候変動・地球温暖化の影響が深刻化し、猛暑や豪雨、巨大ハリケーンなどによる人的・物的災害が大きな経済・社会的負担となり、異常気象を日々実感する状況が地球全体に及んでいる。2015年、国際社会は地球エコシステムと人類社会の未来への危機感を共有し、2つのエポックメーキングな合意に至った。すなわち、21世紀中に脱炭素化を実現し地球温暖化を2℃までにくい止める目標を掲げるパリ協定と、「環境・経済・社会」の17の目標を掲げ2030年までにその統合的達成を目指す国連の持続可能な開発目標(SDGs)である。
2018年4月、我が国が閣議決定した第5次環境基本計画では、パリ協定とSDGsという世界の大潮流を受け止め、目指すべき脱炭素でSDGsを実現するサステナブルな経済・社会の姿として「地域循環共生圏」を提唱し、これが実現する真に持続可能な循環共生型の社会である「環境・生命文明社会」を目指すとしている。
「地域循環共生圏」とは、情報通信技術をはじめテクノロジーをフル活用し、各地域において再生エネルギーや衣食住を支える地域資源の活用をすることで自立・分散型の地域を形成しつつ、地域の特性に応じた人的・物的資源を補完し支え合うネットワークをつくりだすことで、脱炭素でサステナブルな循環共生型の経済・社会構造を目指すものである。森里川海といった自然資本に支えられ、水の循環系に象徴される自然のエコシステムの一部として人類は生存しているという原点にまで立ち返って、この人類生存の基盤であるエコシステムが、テクノロジーの有効活用によりそのポテンシャルを発揮し、いかに健全でありうるかという視点で地域や経済・社会をとらえ直すものである。循環・共生という生命・生態系の基本原理すなわち自然界の摂理に人類活動が調和することにより、地下資源依存型の大量生産・大量消費・大量廃棄の経済から脱却し、結果的に脱炭素が達成されることになる。日本の産業界はテクノロジーが切り拓く調和型の未来社会Society5.0を提唱しているが、「地域循環共生圏」とはSociety5.0が描くスマート・テクノロジーの展開を地域において具体化するものに他ならない。この「地域循環共生圏」に向かった経済・社会の資源配分シフトが今後数十年規模で起こるであろうし、またそれを加速しなければならない。そしてこのシフトこそが世界の新たな成長の原動力となるであろう。中国では一足先に「生態文明建設」を国家方針として掲げたが、我が国からの「環境・生命文明社会」の創造、それを具体化する「地域循環共生圏」はまさしくこれと軌を一にしており、今後日本から世界に発信していくこととしている。
パリ協定により、今世紀後半には従来通りには化石燃料を燃やせない時代が到来するというコンセンサスが共有される中で、すでに脱炭素でSDGsを実現するサステナブルな経済・社会を目指したビジネスの潮流が世界において主流化し、産業構造、経済・社会システムの転換が始まっている。そして、これを金融面で牽引しているのが、ESG投資の顕著な拡大である。2015年のパリ協定とSDGsの採択以降、ESG投資は世界で急拡大をしている。日本のESG投資が世界に占めるウエイトはまだ小さいものの直近の2年で2.4倍になった。またこの文脈で大手の金融機関や機関投資家が石炭関連投融資から撤退するダイベストメントも広がっている。このような資金の流れの潮流により、脱炭素でサステナブルな経済・社会に沿ったビジネスが成長すると同時に、これに逆行するビジネスは、資金調達等が困難になってきている。また、主要なグローバル大企業が、事業活動に必要なエネルギーを全て再生エネルギーで賄うことを目指すRE100に参画してきており、参画企業数は今後さらに増えていくと見られる。この動きはサプライチェーン全体での動きになりつつあり、調達先となる地域の企業で環境経営に優れたところにはグローバル大企業からも注文が入る一方で、環境面で遅れた企業はサプライチェーンから外されるということが現実になってきている。
21世紀は本書『中国都市ランキング』が指摘するように「大都市の世紀」である。グローバルな資源獲得、生産、流通上の便益や効率性を求めての競争の結果、本書の研究対象である中国をはじめ、世界においては人口移動とビジネスの集中が都市化をもたらした。都市機能の充実が更なる大都市化につながり、周牧之教授が早くから着目してきたようにメガロポリス化は世界の必然の趨勢であった。そのプロセスが進む中で世界は気候変動や資源枯渇をはじめとした環境制約に直面した。今やこの環境制約に目覚めることで人類の文明パラダイムの転換が起きつつある。今後の都市においては、脱炭素化とSDGsの要請を受けて、都市のサステナブルなエコシステムの構築が最重要課題となり、それへの移行こそが新たな成長をもたらすであろう。「環境、社会、経済」の三大項目で構成される本書の〈中国都市総合発展指標〉が「生態環境」を広義に評価し、指標化によりその質的充実度を促す役割を担うことは極めて重要である。
SDGsの国連での採択以前から、都市化という大潮流の中でいかに生態環境調和を実現するかという問題意識を持ち、周牧之教授を統括プロデューサーに、我が国環境省と中国国家発展改革委員会発展計画司の協力プロジェクトとして、環境、社会、経済のトータルな観点で都市を評価することを研究してきた。その研究がベースになり、〈中国都市総合発展指標〉がサステナブルな経済・社会への移行に寄与すべく発展していることを心から喜びたい。
1. 新型コロナウイルス禍が世界の大都市を直撃
新型コロナウイルスパンデミックが世界の都市を襲い、大きな被害を与えている。なかでも特にニューヨーク、ミラノ、東京、北京などグローバルシティの感染者が際立って多い。
外出自粛、休業要請、そしてロックダウンにより、都市生活は一変した。国内はもとより国境を越えた人の往来も止まった。国際都市を支える航空輸送はストップし、滑走路は離陸の機会を失った旅客機で埋め尽くされた。インバウンドの女王ともてはやされた豪華客船は、大規模感染源と化し、地域間を結ぶ高速鉄道(新幹線)は大幅減便され、ひと気の無い車両が行き来している。
日本は観光立国を掲げ、昨年まで国際観光客数を順調に伸ばしてきた。2019年度の国際観光客数が3,188万人であったことを踏まえ、2020年には4,000万人の受け入れを目指していた。しかし、コロナショックで4月以降、海外観光者数はほぼゼロとなった。
都市の日常生活も一変した。オフィスワークからテレワークへの強制的な切り替えによりオフィス街は静まり返った。賑やかだった商店街も閑散とした。分業と交流を糧とした高密度の大都市は、「三密」回避の恐怖により「疎の社会」へと化した。
2. 大都市の医療崩壊
新型コロナウイルスはまず、大都市の医療システムを脅かした。
中国の武漢市は新型コロナウイルスの試練に世界で最初に向き合った都市であった。同市は27カ所の三甲病院(最高等級病院)を持ち、医師4万人、看護師5.4万人そして医療機関病床9.5万床を擁する。
雲河都市研究院が公表した「中国都市医療輻射力2019」全国ランキングで武漢は第6位の都市である。しかし、武漢のこの豊富な医療能力が新型コロナウイルスの打撃により、一瞬で崩壊した。
ニューヨークやミラノといった国際都市の医療キャパシティも同様に、新型コロナウイルスに瞬く間に潰された。第二波にある東京都も目下、医療システム崩壊の危機に直面している。新型コロナウイルスはまさに全世界の都市医療能力を崩壊の危機に晒している。
新型コロナウイルス禍による都市の「医療崩壊」は、以下の三大原因によって引き起こされた。
(1) 医療現場がパニックに
新型コロナウイルス禍のひとつの特徴は、感染者数の爆発的な増大だ。とりわけオーバーシュートで猛烈に増えた感染者数と社会的恐怖感とにより、感染者や感染を疑う人々が医療機関に大勢駆け込み、検査と治療を求めて溢れかえった。病院の処置能力を遥かに超えた人々の殺到で医療現場は混乱に陥り、医療リソースを重症患者への救済にうまく振り向けられなくなった。医療救援活動のキャパシティと効率に影響を及ぼし、致死率上昇の主原因となってしまった。さらに重大なことに、殺到した患者、擬似患者、甚だしきはその同行家族さえ長期にわたり病院の密閉空間に閉じ込められ、院内感染という大災害を引き起こした。
人口1千人当たりの医師数でみると、イタリアは4人で、医療の人的リソースは国際的に比較的高い水準に達している。しかし新型コロナウイルスのオーバーシュートで医療機関への駆け込みが相次ぎ、医療崩壊を招いた。
アメリカ、日本、中国の人口1千人当たりの医師数は、各々2.6人、2.4人、2人であり、医療の人的リソースはイタリアに比べ、はるかに低い水準にある。
よくも悪くも中国の医療リソースは中心都市に高度に集中している。武漢は人口1千人当たりの医師数は4.9人で全国の水準を大きく上回る。武漢と同様、医療の人的リソースが大都市に偏る傾向はアメリカでも顕著だ。ニューヨーク州の人口1千人当たりの医師数は4.6人にも達している。
しかし武漢、ニューヨークの豊かな医療リソースをもってしても、新型コロナウイルスのオーバーシュートによる医療崩壊は防ぎきれなかった。5月31日までに、中国の新型コロナウイルス感染死者数の累計83.3%が武漢に集中していた [1]。その多くが医療機関への駆け込みによるパニックの犠牲者だと考えられる。
東京都は人口1千人当たりの医師数が3.3人で、これは武漢より低く、ニューヨークと同水準にある。日本政府は当初から、医療崩壊防止を新型コロナウイルス対策の最重要事項に置いていた。新型コロナウイルス検査数を厳しく制限し、人々が病院に殺到しないよう促した。目下、こうした措置は一定の効果を上げ、医療崩壊をかろうじて食い止めている。しかし、検査数の過度の抑制は、軽症感染者及び無症状感染者の発見と隔離を遅らせ、治療を妨げると同時に、莫大な数の隠れ感染者を生むことに繋がりかねない。軽症感染者、無症状感染者の放置は日本の感染症対策に拭い切れない不穏な影を落としている。
(2) 医療従事者の大幅減員
ウイルス感染による医療従事者の大幅な減員が、新型コロナウイルス禍のもう1つの特徴である。
とくに、ウイルス感染拡大の初期、各国は一様に新型コロナウイルスの性質への認識を欠いていた。マスク、防護服、隔離病棟などの資材不足がこれに重なり、医療従事者は高い感染リスクに晒された。こうした状況下、PCR検体採取、挿管治療など、暴露リスクの高い医療行為への危険性が高まった。これにより各国で現場の医療人員の感染による減員状態が大量に起こった。オーバーシュートで、もとより不足していた医療従事者が大幅に減員し、危機的状況はさらに深刻化した。
強力な感染力を持つ新型コロナウイルスは、医療従事者の安全を脅かし、医療能力を弱め、都市の医療システムを崩壊の危機に陥れている。
(3) 病床不足
新型コロナウイルス感染拡大後、マスク、防護服、消毒液、PCR検査薬、呼吸器、人工心肺装置(ECMO)などの医療リソースの枯渇状況が各国で起こった。とりわけ深刻なのは病床の著しい不足である。感染力の強い新型コロナウイルスの拡散防止のため、患者は隔離治療しなければならない。とりわけ重症患者は集中治療室(ICU)での治療が不可欠だが、実際、各国ともに病床の著しい不足に喘いでいる。
問題なのは、すべての病床が新型コロナウイルス治療の隔離要求に耐えるものではない点にある。これに、爆発的な患者増大が加わり、病床不足が一気に加速した。
3. 迅速な支援がカギ
武漢の医療従事者大幅減員に鑑み、中国は全国から大勢の医療従事者を救援部隊として武漢へ素早く送り込んだ。武漢への救援医療従事者は最終的に4万2,000人に達した。この措置が武漢の医療崩壊の食い止めに繋がった。
さらに武漢は国の支援で迅速に、専門治療設備の整う火神山病院と雷神山病院という重症患者専門病院を建設し、前者で1,000床、後者で1,600床の病床を確保した。このほかに、武漢は体育館などを16カ所の軽症者収容病院へと改装し、1万3,000床の抗菌抗ウイルスレベルの高い病床を素早く提供し、軽症患者の分離収容を実現させた。先端医療リソースを重症患者に集中させ、パンデミックの緩和を図った。武漢は火神山、雷神山両病院そして軽症者収容病院建設により、病床不足は解消された。
感染地域に迅速かつ有効な救援活動を施せるか否かが、新型ウイルスへの勝利を占う1つのカギである。しかし、全ての国がこうした力を備えているわけでない。ニューヨーク、東京の状況からすると、医療リソースがかなり揃っている先進国でさえ救援できるに足りる医療従事者を即座に動員することは難しい。
最も深刻なことは、医療リソースに著しく欠ける発展途上国、アフリカはいうに及ばず巨大人口を抱えるアジアの発展途上国の、人口1千人当たりの医師数はインドが0.8、インドネシアは0.3である。1千人当たりの病床数は前者が0.5、後者は1だ。こうした元々医療リソースが稀少かつ十分な医療救援能力を持たない国にとって、新型コロナウイルスのパンデミックで引き起こされる医療現場のパニックは悲惨さを極める。グローバルな救援力をどう組織するかが喫緊の解決課題となっている。問題は、大半の先進国自体が、新型コロナウイルスの被害の深刻さにより、他者を顧みる余裕を持たないことにある。
4. グローバルサプライチェーンを寸断
新型コロナウイルス禍はグローバルサプライチェーンを寸断させ、産業活動に大きな打撃を与えた。
IT革命、輸送革命、そして冷戦後の安定した世界秩序から来る安全感によって製造業のサプライチェーンは、国を飛び出し、グローバルに展開した。工場やオフィスの最適立地が世界規模で一気に進んだ。中国の沿海部での急激な都市化、メガロポリス化がまさにグローバルサプライチェーンによってもたらされた。
グローバルサプライチェーンは世界規模に複雑に組み込まれて進化してきた。例えば、アメリカのカリフォルニアで設計され、中国で組み立てられるiPhoneの場合、その部品調達先の上位200社だけとってみても28カ国・地域に及ぶ。
しかし新型コロナショックによるロックダウン、国境封鎖など強力な措置により、グローバルに巡らされたサプライチェーンは寸断され、これまで当たり前のように動いていた供給体制は機能不全に追い込まれた。海外からの部品供給が止まったことで日本国内の工場は操業停止のケースが相次いだ。
「世界の工場」中国もサプライチェーンの寸断で大きな被害を受けることとなった。雲河都市研究院が公表した「中国都市製造業輻射力2019」ランキングトップ10位都市の深圳、蘇州、東莞、上海、仏山、寧波、広州、成都、無錫、廈門は、2020年第一四半期の一般公共予算収入が軒並みマイナス成長となった。とくに、深圳、東莞、上海、仏山、成都、廈門の6都市の同マイナス成長は二桁にもなった。中国の貨物輸出額の50%を実現してきた同トップ10都市は、まさに世界に名だたる製造業都市である。これら都市の大幅な税収低迷は、中国の輸出工業が大きな試練に晒されていることを意味している。
物理的、一時的な寸断よりは、長期的な価値判断の変化がより大きな影響を及ぼす。先行きの不透明さや不確実性により、企業経営は効率と成長一辺倒の姿勢から、もしもの事態に備えた在庫のあり方や資金確保など「冗長性」が重視されるようになった。「Just in time」から「Just in case」へと急転換する経営姿勢が、サプライチェーンのあり方に大きな影響を及ぼしつつある。
サプライチェーンの過度の海外依存も国の危機管理の脆さを露呈した。例えば、アメリカの医薬品の材料の72%は外国産である。抗生物質に限ると97%が外国産に頼っている。こうした医療資材の海外依存は、オーバーシュート時における医療品不足に拍車をかけた。日本でもマスクの海外からの供給が止まったことで、市場からその姿が消えた。本来、効率を優先して組み立てられたグローバルサプライチェーンは、経済の安全保障化(Securitization)により、再組織の機運が高まっている。
もとよりグローバルサプライチェーン自体のあり方も変質している。従来のサプライチェーンのグローバル化は、労働集約型の部分と、知識集約型の部分を地理的に分けて最適立地を進めてきた。しかしここに来てむしろ得意の部分と不得意の部分を地理的に分けてつなげ、最適立地を促すようになった。すると、サプライチェーンがさらに複雑かつ高速に絡み合うことになる。そうした変化がサプライチェーンを潤滑に進めるための契約の集約度 [2]を一層高める。よってサプライチェーンに関わる国の法制度の質が、この契約集約的な生産体制の効率を左右することとなる。
だが、こうした動きはサプライチェーンのグローバル化を止めることはなく、そのより健全な展開を促すであろう。例えば、半世紀前の石油危機では石油のグローバル供給の脆弱性が認識され、それを備蓄で対処した。その後各国は備蓄のキャパシティを高めたが、石油貿易自体は止まらなかった。世界経済の石油貿易に対する依存度はむしろ深まった。
世界経済のグローバルサプライチェーンへの依存度は今後さらに深まるだろう。ただし、サプライチェーンのグローバル展開はグローバリゼーションの回復力をテコに、冗長性、セキュリティ、法制度の質などをキーワードとして再編され、進化していくだろう。
5. 地球規模の失敗
大航海時代から今日まで、人類は一貫して感染症拡大の脅威に晒され、この間、幾度となく悲惨な代償を払ってきた。例えば、1347年に勃発したペストで、ヨーロッパでは20年間で2,500万もの命が奪われた。1918年に大流行したスペインかぜによる死者数は世界で2,500万〜4,000万人にも上ったとされる。
ここ100年余りにわたる抗菌薬とワクチンの開発及び普及により、天然痘、小児麻痺、麻疹、風疹、おたふく風邪、流感、百日咳、ジフテリアなど人類の健康と生命を脅かし続けた感染症の大半は、絶滅あるいは制御できるようになった。1950年代以降、先進国では肺炎、胃腸炎、肝炎、結核、インフルエンザなどの感染疾病による死亡者数を急激に減少させ、癌、心脳血管疾患、高血圧、糖尿病など慢性疾患が主要な死因となった。
感染症の予防と治療で勝利を収めたことで、人類の平均寿命が伸び、主な死因も交代した。世界の国々の中でもとりわけ先進国の医療システムの焦点は、感染症から慢性疾患へと向かった。その結果、各国は感染症予防と治療へのリソース投入を過少にし、現存する医療リソースを主として慢性疾患に傾斜させる構造的な問題を生じさせた。医療従事者の専門性から、医療設備の配置、そして医療体制そのものまで新型ウイルス疾患の勃発に即座に対応できる態勢を整えてこなかった。
その意味では、新型コロナウイルスが全世界に拡散した真の原因は、国際的な人的往来の速度と密度ではなく、人類が長きに渡り、感染症の脅威を軽視したことにこそある。
世界経済フォーラム(WORLD ECONOMIC FORUM)が公表した「グローバルリスク報告書2020(The Global Risks Report 2020)」の、今後10年に世界で発生する可能性のある十大危機ランキングに、感染症問題は入っていなかった。また、今後10年で世界に影響を与える十大リスクランキングでは、感染症が最下位に鎮座していた。
不幸にして世界経済フォーラムの予測に反し、新型コロナウイルスパンデミックは、人類社会に未曾有の打撃を与えた。新型ウイルスとの闘いにおいて、武漢、ニューヨーク、ミラノといった分厚い医療リソースを持つ大都市さえ対策が追いつかず、悲惨な代償を払うことになった。
ビル・ゲイツは2015年には、ウイルス感染症への投資が少な過ぎる故に世界規模の失敗を引き起こす、と警告を発していた [3]。新型コロナウイルス禍はビル・ゲイツの予言を的中させた。
6. 科学技術進歩を刺激
緊急事態宣言、国境封鎖、都市ロックダウン、外出自粛、ソーシャルディスタンスの保持など、各国が目下進める新型コロナウイルス対策は、人と人との交流を大幅に減少かつ遮断することでウイルス感染を防ぐことにある。こうした措置は一定の成果を上げるものの、ウイルスの危険を真に根絶させ得るものではない。ウイルス蔓延をしばらく抑制することができても、その効果は非常に脆弱だと言わざるを得ない。次の感染爆発がいつ何時でも再び起こる可能性がある。
しっかりとした対策が成果をあげるにはやはり科学技術の進歩に頼るほかない。新型コロナウイルス危機勃発後、アメリカをはじめとする各国でPCR検査方法を幾度も更新し、検査結果に要する時間を大幅に短縮した。安価で、ハイスピードかつ正確な検査方式が大規模な検査を可能にした。特効薬とワクチンの開発においても各国がしのぎを削っている。
人類は検査、特効薬、ワクチンの三種の神器を掌握しなければ、本当の意味で新型コロナウイルスをコントロールし、勝利を収めたとは言えないだろう。
危機はまた転機でもある。近現代、世界的な戦争や危機が起こるたびに人類は重大な転換期に向き合い、科学技術を格段に進歩させてきた。第二次世界大戦は航空産業を大発展させ、核開発の扉を開けるに至った。冷戦では航空宇宙技術の開発が進み、インターネット技術の基礎をも打ち立てた。新型コロナウイルスも現在、関連する科学技術の爆発的な進歩を刺激している。
新型コロナウイルスが作り上げた緊迫感は技術を急速に進歩させるばかりでなく、技術の新しい進路を開拓し、過去には充分に重視されてこなかった技術の方向性も掘り起こす。例えば、漢方医学は武漢での抗ウイルス対策で卓越した効き目をみせ、注目を浴びている。漢方医学は世界的なパンデミックに立ち向かうひとつの手立てになりうる。
オゾンもまた偏見によりこれまで軽視されてきた。筆者は2020年2月18日にはオゾンについて論文を発表し、「自然界と同レベルの低濃度オゾンであっても新型コロナウイルスに対して相当の不活化力を持つ」との仮説を立て、新型コロナウイルス対策として、オゾンの強い酸化力によるウイルス除去を呼びかけた [4]。オゾンは室内空間のすべてに行き届き、その消毒殺菌に死角は無い。また、酸化力によるオゾンの消毒殺菌は有毒な残留物を残さない。さらに、オゾンの生成原理は簡易で、オゾン生産装置の製造は難しくない。オゾン発生機のサイズは大小様々あり、個室にも大型空間にも対応できる。設置が簡単なため、バス、鉄道、船舶、航空機などどこでも使用可能である。こうしたオゾンの特質を利用し、室内のウイルス感染を抑えることができる。
オゾンは非常に優れた殺菌消毒のパワーを持つが、個人差はあるものの一定の濃度に達した場合に人々に不快感を与え、また、粘膜系統に刺激を与えることもある。そのため、目下、主に無人の空間で使用されている。有人空間の利用を可能とするには、オゾン濃度のコントロールが必要である。自然界に近い濃度のオゾンを室内に取り入れられれば、人々に不快感を与えることはない。しかし問題は目下、低濃度のオゾンを高精度に測定するセンサーが大変高価なことである。高精度のオゾンセンサーを容易に使えないため、普及型低濃度オゾンのコントロールはいまだ実現できていない。オゾンセンサーの開発にも技術の急激な進歩が期待される。
7. 一気に加速するデジタル化
新型コロナウイルスショックは世の中の価値判断の基準を一気に変えた。これから成長する企業とそうではない企業に対するジャッジメントは、時価総額により見て取れる。コロナパンデミック以降、投資マネーが次の成長企業を探して急激に動いていることで、時価総額の順位は激しく変動している。
まず、新型コロナウイルス禍の影響で、他業種は軒並み時価総額を減らしているのに対して、IT企業が大きく伸びた。2020年5月初め、アルファベット(グーグル持ち株会社)、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフトを合わせたGAFAM5社の時価総額は、東証一部約2,170社の合計を上回った。
今から30年前、平成が幕を開けた1989年、世界の企業時価総額ランキングトップ10企業のうち、7社が日本企業で占められた。通信、金融、電力の企業であった。IBMは大型コンピューター業界の巨人として同ランキングで第6位を獲得し、かろうじて当時のIT業界の存在感を示していた。
これに対して2020年8月末には、世界の企業時価総額ランキングトップ10企業のうち、7社がネット関連のIT企業となった。特にアップルは2兆ドルを突破し(米国初)、企業時価総額世界第1位に躍り出た。GAFAMに続き、中国のネット関連企業、テンセントとアリババがそれぞれ同ランキングで第7位、第8位だった。
企業の成長性に対する期待感を表すプライス・トゥー・レベニュー(Price to Revenue:時価総額対売上の倍率)でもIT企業が高く、例えばフェイスブックの場合は9倍となる。それに対して、トヨタを含む自動車メーカーの場合は1倍に割り込むものがほとんどで、産業による明暗が大きく分かれた。しかし同じ自動車メーカーでもテスラの場合、10倍になった。テスラの時価総額が2020年7月、トヨタを抜いて自動車産業のトップに立ったことが話題になった。売上はトヨタの11分の1、販売台数は30分の1でしかない。
テスラにIT企業並みの成長への期待感が出た最大の原因は、同社が、自動車を、ソフトのダウンロードにより性能のアップデートを可能とした「電気で走るIT機器」へと大変身させたことにある。シリコンバレー発の自動車メーカーと、伝統的な自動車メーカーの発想は違う。発想の斬新さに、投資家がテスラを次代のリィーディングカンパニーとして高く評価した。新興勢力のテスラは既存の王者を追い抜き、自動車業界の時価総額で世界首位となった。8月末、世界の企業時価総額ランキングにおけるテスラの順位は7月の第22位から、第10位へと大躍進した。
非IT業界でも、デジタルトランスフォメーション(DX)の巧拙が企業の明暗を分けている。DXに遅れた企業は、業績もマーケットの評価も振るわない場合が多い。デジタル化の対応力が企業の運命を左右している。コロナショックで小売業界が厳しい試練に晒される中、アメリカでは5月7日に高級百貨店のニーマン・マーカスが、5月19日には大衆百貨店のJCペニーが、相次ぎ経営破綻した。これに対してウォルマートは2〜4月期の純利益が、前年同期比4%増の39億9,000万ドルに達した。これを牽引したのは売上高が同7割増したネット販売だった。
メディア業界でも地殻変動が起こっている。娯楽・メディアの王者ウォルト・ディズニーの時価総額世界ランキングが下がったのに対し、動画コンテンツ配信新興勢力のネットフリックスが、時価総額を急上昇させ、同順位は前者のそれを超えた。
8. 接触の経済性が交流経済を後押し
グローバリゼーションの中で、大都市化そしてメガロポリス化も一層世界の趨勢となった。1980年から2019年の間、世界で人口が100万人以上純増したのは326都市となり、この間これらの都市の純増人口は合計9億4,853万人にも達した。とりわけ、人口が1,000万人を超えたメガシティは1980年の5都市から、今日33都市にまで膨れあがった。こうしたメガシティはほとんどが国際交流のセンターであり、世界の政治、経済発展を牽引している。これらメガシティの人口は合わせて5億7,000万人に達し、世界の総人口の15.7%をも占めている。
グローバリゼーションが進むにつれ、国際間の人的往来はハイスピードで拡大し、世界の国際観光客数は30年前の年間4億人から、2018年には同14億人へと激増した。しかし、国際間における大量の人的往来は新型コロナウイルスをあっという間に世界各地へ広げ、パンデミックを引き起こした。国際交流が緊密な大都市ほど、新型コロナウイルスの爆発的感染の被害を受けている。
新型コロナウイルスのパンデミックで、各国はおしなべて国境を封鎖し都市をロックダウンして国際間の人的往来を瞬間的に遮断した。グローバリゼーションの未来への憂慮、国際大都市の行方に対する懸念の声が絶えず聞こえてくるようになった。
こうした懸念に答えるためには巨大都市化の本質を理解する必要がある。200年余りの近代都市化のプロセスにおいて、都市を支える経済エンジンは実に目まぐるしく変化してきた。この経済エンジンの変化は、巨大都市化を突き動かしている。
工業社会から情報社会へ急速にシフトする中、情報革命が都市のあり方をどう変えるかについて希望的観測がある。人々は煩わしい大都市から離れ、田舎の牧歌的な生活を楽しみながら、情報社会における高い生産性を実現できるというものである。これであれば、知識経済における大都市の役割と必然性はかなり薄まる。ところが実際には、大都市の役割は薄まるどころか、強まる一方である。産業と人口を大都市へ集中させる力は、工業社会より情報社会の方が格段に強くなっている。
なぜこのような事態が生じたのか?それに答えるためには知識経済の本質を探らなければならない。知識経済の本質は、人間という情報のキャリアにある。情報キャリアとしての人間が、情報交換や議論の中で、知の生産と情報の判断を行うことが知識経済の本質である。効率的な情報交換と議論こそが、知識経済の生産性の決め手となる。
しかし、人間の持つ情報は2種類ある。1つはITでやりとりできる「形式知」である。もう1つはITでやりとりできないか、あるいは、人と人との信頼関係によってしか流れない「暗黙知」である。前者と比べ後者ははるかに重要である。その意味では、情報の空間克服技術であるIT のみに頼る情報交換や議論は不完全なものである。つまり、IT を通じて外に出せる情報と、IT 社会においても外に出せない情報を人間は持っている。外に出せる情報は情報革命によって、毎秒30万キロのスピードで世界を駆け巡っている。情報技術の向上はまた外に出せない情報を持つ人と人との接触を増やしている。
上記の分析に基づけば、工業経済では「規模の経済性」原理が働くのに対して、知識経済では「接触の経済性」[5]原理が働くと言えよう。知識経済の生産性において、接触の多様性、意外性、そしてスピードは非常に重要である。情報の均一性を重んじる工業経済とは対照的に、知の生産においては同質の情報しか持たない人間同士の接触より、異質の情報キャリア間の接触の方が重要性を増す。情報キャリアの多様性と接触の意外性、そして接触のスピードは情報経済の生産性の決め手となる。その意味では、知識経済は正に「交流経済」である。
知識経済の時代は人と人との触れ合いの時代である。フェイス・トゥ・フェイスコミュニケーションの中で、瞬間的に情報と知識の創造と交換が起こる。多種多様な情報キャリアたる人々が往来し、生活する大都市は、接触の多様性、意外性、そしてスピード性を実現できる格好の空間である。こうした都市で知識は企業、組織の境界を超えてスピルオーバー(漏出)効果が働き、知識の生産性が一層高まる。
人と人とが触れ合うプラットフォームを提供する場としての重要性が高まる国際大都市の役割は、ますます大きくなっている。これがゆえに、知識経済における大競争に勝ち残った国際大都市への、経済と人口の集中は、より進んできた。
ジェット機、コンテナ輸送、高速鉄道といった輸送革命が、経済的な地理、心理的な地理を縮めてきた。情報革命もこうした地理感覚をさらに圧縮してきた。コロナ禍で急速に進むオンライン化は、結果的に情報の一層のグローバル化に拍車をかける。よって経済地理、心理的地理は一層縮まるだろう。オンラインとフェイス・トゥ・フェイスとの組み合わせによる新しいコミュニケーションスタイルが生まれ、国際大都市の役割はさらに高まるだろう。
9. グローバリゼーション、そして大都市化は止まらない
IT産業は代表的な交流経済である。雲河都市研究院が公表した「中国IT産業輻射力2019」のトップ10都市は、北京、深圳、上海、成都、広州、杭州、南京、福州、武漢、西安であった。この10都市は中国のIT産業従業者数の6割を有し、73%のメインボード(香港、上海、深圳)に上場するIT企業を持つ。
この10都市は、共通して中国を代表する国際都市であると同時に、人口流入都市でもある。IT産業は、まさに国際交流を糧に成長し、都市の繁栄と人口増大をもたらしている。
日本では、一都三県からなる東京圏の人口も、1950年の1,000万人台から今日の3,700万人へと膨れ上がった。そのコアとなる東京都は2020年5月1日に人口が1,400万人を突破した。2009年4月1日の1,300万人突破から11年で、100万人増加した。東京の2019年の合計特殊出生率は1.15と全国最低だ。人口増の7割以上が都外からの転入による社会増だった。
東京は、日本でダントツにIT輻射力の高い都市である。東京圏には東証メインボード上場のIT企業の8割が集中し、IT産業従業者数は100万人を超えている。
東京圏は、ITを始め魅力的な仕事が多いだけでなく、225カ所の大学も立地し、全国の4割に当たる118万人の大学生、全国の半数となる15万人の留学生を集めている。
総務省によると2019年、生産年齢人口(15〜64歳)の東京への転入超過数は、9.6万人に達した。
日本政府は早い段階から東京圏への一極集中是正にさまざまな政策を打ち出しているが、東京への人口流入を止めることはできなかった。
コロナパンデミックの中で、東京から地方へ人口が流出する予測が高まっている。しかし、筆者は東京都市圏のシュリンクはそう簡単に進まないと見ている。国際大都市を魅力と感じる人々が集まってくる傾向がこれからも続く。
さらに注目すべきは、世代を重ねて人口が東京圏に定着してきたことである。現在、首都圏 [6]在住者の7割が東京圏出身であり、地方出身は3割だ。首都圏で生まれた30歳未満の若い世代は、両親とも首都圏出身者が5割に達する [7]。地方との縁の薄い人々が首都圏で増えているなかで、コロナショックがあっても地方への人口の逆流はあまり期待できない。実際、NHKが6月に都民1万人を対象に実施したアンケート調査によると、東京に住み続けたいかとの質問に対して、コロナ禍の真最中にも関わらず、87%が住み続けたいと回答した [8]。
大都市の人口密度がコミュニケーションの密度を高め、効率性、生産性、創造性を促してきた。最も人口集積の高い東京都の一人当たりの所得水準は、日本で最も高く、全国平均の約1.7倍にもなる。この高い所得水準もさらに若者を惹きつけている。
しかし、新型コロナの影響で3密が危険視され、人と人の距離が隔たった。「疎の社会」がニューノーマルになると考える人も少なくない。これに対して筆者は、より楽観的である。安くて性能に優れたオゾンセンサーが開発できれば、有人空間でオゾン利用が可能になる。これにより、室内における飛沫感染が解消され、3密問題は根本的に解決する。人と人の距離は疎から密に戻すことができると確信している。
グローバル化に猛進する21世紀はすでに3度のグローバル的なショックを受けている。ひとつは、2001年の9.11のテロ事件で、2度目は2008年リーマンショック、3度目は今回の新型コロナウイルス禍である。しかし、やがて人類は、新型コロナウイルス禍を乗り越える。新型コロナウイルスパンデミックを収束させた後には、より健全なグローバリゼーションとより魅力的な国際大都市が形作られるであろう。
10.〈中国都市総合発展指標2018〉の特色
〈中国都市総合発展指標〉は、データをもって価値判断を実証する側面が強い。環境、社会、経済の三つの側面から都市を評価すると同時に、「DID」「輻射力」などの概念を数字化し、中国で人口密度と輻射力の大切さを植え付けた。筆者が20年前から提唱してきたメガロポリスや都市圏政策も、同指標の力を借りて一層浸透できた。〈中国都市総合発展指標〉のメインレポートは、2016年度は「メガロポリス発展戦略」、2017年度は「中心都市発展戦略」、2018年度は「大都市圏発展戦略」として展開してきた。また、こうした戦略を促すために、同指標をベースに「中心都市&都市圏発展指数」をも開発し、公表した。
現に、中国政府はメガロポリス、中心都市、都市圏などをコアに、都市化政策を展開するようになってきた。同指標に関わった専門家らにはいささかの達成感がある。
〈中国都市総合発展指標〉の評価の公開度もアップしてきた。総合ランキングの公表は2016年度のトップ20都市から、2017年度はトップ150都市へ、そして2018年度になると全298都市になった。
〈中国都市総合発展指標〉のデータ構成にも工夫がある。従来、都市に関連する指標は、統計データによるものであった。しかし、統計データだけでは複雑な生態系と化した都市を描き切れない。〈中国都市総合発展指標〉は、統計データのみならず、衛星リモートセンシングデータ、そしてインターネット・ビックデータをも導入し、都市を感知する「五感」を一気にアップさせた。現在、指標のデータリソースは、統計、衛星リモートセンシング、インターネット・ビックデータは、各々ほぼ3分の1ずつの分量となった。〈中国都市総合発展指標〉は、こうした垣根を超えたデータリソースを駆使し、都市を高度に判断できるマルチモーダルインデックス(Multimodal Index)へと進化した。
2020年7月に米PACE大学出版社から〈中国都市総合発展指標〉の英語版が出版された。これで、中国語版、日本語版、英語版が揃った。これを契機に、指標をさらに進化させていく所存である。
コロナ禍のさなか、大切な研究仲間、山本和彦さんの訃報にふれた。山本さんは森ビル副社長の時代から「江蘇省鎮江ニューシティマスタープラン」や〈中国都市総合発展指標〉の議論に参加してくださり、国内外での研究会や飲み会でたくさんの叡智を授かり、幾度も楽しい時間を一緒に過ごした。ご退院後にお手紙をいただき、体調が回復したら吉祥寺で飲みましょうとの嬉しいお言葉を頂戴していた。これが実現できなくなったいま、山本さんのご期待に応えるべく一層の研究成果を出し続けるほかない。
[1] 2020年5月31日以降に武漢では新型コロナウイルス感染による死者は出ていない。
[2] 「米ハーバード大学ネイサン・ナン教授は、複雑なサプライチェーンを通して生産される製品は様々な取引を伴うので「契約集約的」という言い方もできると指摘する」、猪俣哲史「制度の似た国同士で分業へ 国際貿易体制の行方」、『日本経済新聞』2020年7月14日朝刊。
[3] ビル・ゲイツ氏、2015年3月「TED TALK」での講演「The next outbreak? We’re not ready」。
[4] オゾンに関する筆者の論文はまず中国語版が2020年2月18日に「这个“神器”能绝杀新冠病毒」とのタイトルで中国の大手メディアである中国網で発表された。その後、英語版はOzone: a powerful weapon to combat COVID-19 outbreakのタイトルで2月 26日に China.org.cnで発表された。日本語版は「オゾンパワーで新型コロナウイルス撲滅を」とのタイトルで2020年3月19日にチャイナネットで発表された。半年後の8月26日に学校法人藤田医科大学は、同大学の村田貴之教授らの研究グループが、低濃度のオゾンガスでも新型コロナウイルスに対して除染効果があるとの実験結果を発表した。この実験は筆者の2月論文の仮説にとって貴重なエビデンスとなった。
[5] 接触の経済性について、詳しくは、周牧之著『中国経済論—高度成長のメカニズムと課題』日本経済評論社、2007年、pp231〜233を参照。
[6] 首都圏整備法は、首都圏を埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県および山梨県と規定している。
[7] 斉藤徹弥「首都圏出身者は地方を向くか」、『日本経済新聞』2020年7月16日朝刊。
[8] NHK「東京都知事選 都民1万人アンケート」2020年6月21〜24日。
〈中国都市総合発展指標〉を手にして、「よくぞかくも斬新なアイデアから生み出されたものだ」と感心し、しばらくすると「当然あってしかるべき研究成果」であり、これからは多くの企業が真剣にこの書を参考にして進出先の選定にあたり、若い学生たちは就職先を選ぶ時の手がかりの一つにするのではないか、との印象をもった。さらに重要なことは指標対象となった都市の行政は、総合指標の改善を目指すのか、特色ある都市発展のために力を入れるべきテーマを絞るのかという、新しい試みが生まれるであろうと、わくわく感を与えてもらった。
ところで私は、鄧小平氏が登場していよいよ中国の改革開放路線が始まろうとしていたとき、ある中国人の国際政治研究者が中国の将来に向けて為政者が自戒すべきことの第一として、「巨象も流砂に倒れる」ということをいつも念頭においておくことを挙げられたのを記憶している。同氏の主張には、流砂になるリスクは自国の人民のみならず、周辺諸国にもあると指摘していた。
その後40年間、中国は激動する世界の政治経済に翻弄されながらも、この戒めから逸れることなく顕著な前進を遂げてきた。とくに経済面では、改革開放路線の下で1990年代から2010年までの成長は著しく、GDPで日本を抜き米国に次ぐ世界第2の大国となった。もちろん歴史を遡れば18世紀ごろまでの、経済が農業主体であった時代には中国が世界第1位の経済大国であった。その後産業革命による技術の発展、分業化・工業化の進展、貿易の活発化により世界の成長センターは欧州、米国へと移っていった。この経済発展は都市化をもたらし、都市化が経済成長をさらに促していった。まさしく農業時代にはほとんど見られなかった経済成長が実現したのは、工業化と都市化の賜物でもある。遅ればせながら中国の世界経済大国への復帰も、この路線に乗るものであった。
しかしこの経済成長は国民経済の厚生上大きな問題を引き起した。公害であり、自然災害の増大等の環境破壊であり、農山村地域と都市地域との貧富の格差拡大、それが誘発する働き手人口の大移動、住居・教育・医療問題のひずみ等である。とくに短期間に高度成長を実現してきた国ほどその問題は深刻なものとなった。まず日本がそうであったし、中国はその日本に輪をかけるほど直面する課題が大きい。国土が広大な中国にとって、地域間の成長や所得の格差をならし、均衡ある発展に導くことは至難である。全体の成長速度を抑えれば格差のより深刻な拡大を抑え込むことはできても、そこからは格差是正の芽は生まれてこない。国家の資金配分機能や国有企業、国有銀行の活用も考えられるが、そうした政策の常態化はモラルハザードを生み、経済の効率性を阻害し、自立的な都市の発展に逆行するであろう。
結局は冒頭でも述べたように本書の報告に沿って、各都市当局が競争的に次回の指標改善の努力を続けることではなかろうか。なお医療や教育分野について指標に加えたことも特に評価に値すると思うと同時に、わが国にも本書の共同研究者のようなチャレンジ精神を持った人材がでてくることを切望する。
中国が人口大国であることは日本人の誰もが認識しているだろう。しかし、一人っ子政策の効果もあって、2030年には中国の人口はピークを迎える。その前に、2020年代にはインドに国別人口世界第1位の座を明け渡すと国連は予測している。一方で、中国の都市人口の割合は、国連予測の終年である2050年まで上昇の一途をたどり、都市人口数のピークとなる2045年には10.5億人に達する。2015年から2045年の間に、総人口はほぼ横ばいであるものの、都市人口は2.7億人増加する。つまり、中国では、人口そのものは安定に向かいつつも、農村から都市への人口移動が中国の人々、社会、そして国土や環境に大きな影響を与え続けることになる。
〈中国都市総合発展指標〉が注目されるのは、こうした都市化のうねりが何をもたらしているのかを、総計133の指標で多角的に明らかにしているからである。都市化=農村から都市への人口移動と先に述べたが、それは必ずしも妥当な表現とは言えない。なぜなら、都市であっても、上海市や北京市のように常住人口が戸籍人口を大幅に上回る人口流入都市がある一方で、常住人口が戸籍人口を下回る人口流出都市があるというように都市から都市への人口移動も起こっているからである。中国の都市は、都市化に伴う問題に直面するとともに、かつて筆者が日本の都市で指摘した逆都市化、すなわち都市人口の減少に伴う問題を抱える都市があるという複雑な様相を呈している。
こうした状況の下では、都市を、誰にとってもより豊かで、住みやすく、持続的なものとするための都市政策は、1つのタイプに限定されるべきではない。さらなる都市化の過程にある都市における都市政策と、人口流出に伴う空洞化などに対処しなければならない都市におけるそれとは自ずから目的や内容が異なるからである。
〈中国都市総合発展指標〉は、それぞれの都市の現状を、数字によって示すことを目的としている。そのことを通じて、都市が抱えている問題、解決するべき課題が浮かび上がってくる。すでに中国版が提供され、都市政策のあり方に関する種々の議論を起こしていると聞く。特に、環境、社会、経済という大きく3つに分けた分野で、多数の個別指標を、都市ごとに、可能な限り統一的に掲載しているので、都市の居住環境、社会状況から、経済的な発展に至るまで、各都市の位置を知り、比較しつつ考えることができるというエビデンスベースの都市政策立案に大きな貢献をなすと期待できる。
日本と中国は、文字通り一衣帯水の関係にあり、相互に訪問する機会も多く、それぞれの都市を舞台にしたビジネス活動も今後さらに盛んになる。したがって、日本の企業や研究者にとっても、中国をより深く知ることは大きな関心事であろう。これまで、多くの日本人にとっては、中国を知るとはその長い歴史を知り、日本に与えてきた様々な影響を理解することが中心であったかもしれない。
しかし、本指標は、こうした歴史的理解とは少し異なる切り口、すなわち現代の中国都市社会を客観的に把握する格好の手段を与えてくれる。特に、第2次大戦後の、いや改革開放以降の約40年間において、都市を中心に展開されてきた中国の急速な工業化・近代化が、どのような都市社会を形成してきたのかを理解することは、現代中国を理解するうえで不可欠である。可能な限り統一的にデータを収集、作成するという、種々の困難を伴う画期的な試みによって、本書はこのテーマに挑戦した。本書を通じて、日本人の中国理解がより深まることを期待したい。
都市化が急激に進む中国においては、都市の低炭素化と持続可能な経済発展とをいかに両立させていくのかが大きな課題である。エネルギーの消費が急激に増加し、CO2の排出が世界最大規模になった中国では、居住環境の劣化、交通環境の悪化、水質の汚濁、大気の汚染等、さまざまな問題が生じている。また拡大する都市は生態系に悪影響を及ぼし、生物多様性の減少や、自然資本の劣化をもたらしている。
中国をはじめ急激に成長するアジア都市では、地球環境問題への対応と地域の環境汚染改善を一体的に考える新しいスキームが求められる。私は、エネルギーの低炭素化(Energy)、水質・大気改善、適正廃棄物処理などの地域環境の改善(Environment)、都市と自然の共生(Ecosystem)を統合的に捉える3Eネクサスのアプローチによる生態都市の創造を提唱している。〈中国都市総合発展指標〉は、こうした3Eネクサスに示されるような、グローバルな視点とローカルな視点を融合させ、国際社会に対しても大きなインパクトをもつ統合的な都市指標である。
3Eネクサスの考え方を踏まえると、都市の持続可能な発展のためには、三つの大きな社会のビジョンを目指し、それらを統合化させるアプローチをとることが重要である。
一つ目は低炭素社会で、エネルギーの低炭素化と気候変動の緩和を進めるとともに、地域の水質・大気環境改善との同時達成を目指すものである。とくに成長するアジア都市では、依然としてエネルギー利用が拡大しており、再生可能エネルギーへの大転換やエネルギー効率の飛躍的な向上を図らない限り持続可能性は保証されない。
二つ目は循環型社会で、天然資源と廃棄物量を最小化し、リデュース、リユース、リサイクルの原則で資源を循環的に利用することにより持続可能性を高めていこうとするものである。アジア都市では、都市内の資源循環を進めるとともに、建築物やインフラストラクチュアーの更新においても、資源の循環利用を進める必要がある。
三つ目は自然共生社会で、人間と自然がお互いに相乗効果を生み出すことができるような社会をつくりあげていこうというものである。アジア都市の周辺部では、森林や農地などの良好な農村環境が維持される必要がある。都市は、そうした農村環境が提供する生態系サービスを享受する一方、農村に対してさまざまな支援を行っていくことで、両者のバランスが取れた豊かな自然共生社会をつくりあげていくことができる。
その多くがデルタに位置するアジア巨大都市は、とりわけ気候変動による海面上昇、豪雨・洪水などの極端気象の多発などにより、深刻な被害を受ける可能性が高い。上記3つの社会像の統合による持続可能な社会を目指すことは、こうした被害を軽減するための気候変動適応策としても重要であると考えられる。そうした問題意識を行政や市民と共有し、着実に対策を講じ、その成果をモニタリングしていく必要がある。
その際、非常に複雑な都市システムを俯瞰的・統合的に捉えることが、行政や市民の理解を促すうえで重要となる。都市を支える人工資本とともに、人的資本や自然資本にも注目し、各都市の現状を捉え、そのあるべき持続可能な将来像に導いていく必要がある。
本書が扱う〈中国都市総合発展指標〉は、持続可能な開発の三側面である環境、社会、経済を大項目に据え、発展活力、生活品質、自然生態などの中小項目を置いて、中国の都市を評価するとともに、その発展の方向性を具体的に示すものである。
〈中国都市総合発展指標〉のもう1つの大きな特徴は、表現力に富んだグラフィックを多用することで膨大な情報をわかりやすく提示していることである。このような指標の「見える化」により、中国都市化の現状や各都市の抱える問題と今後のあり方についての認識が高まり、持続可能な都市発展に貢献すると期待される。
ロシアのプーチン大統領が、かつてサンクトペテルブルグの副市長で、まだ無名であった時、初めて日本に来た。彼は日本の新聞記者にいつものありきたりの質問、すなわち、日本の印象はどうかと聞かれて、「都市に切れ目がない」と答えた。それを聞いてとても新鮮に感じたことを覚えている。たぶん、東海道新幹線の車窓から外を眺めての感想であろう。
確かにロシアでは都市と都市の間はうっそうとした森林であることが多い。しかし、日本では、俗に言う東海道メガロポリスという国土の10%に満たない地域に約半分の人口が住んでいる。人工衛星からとった夜の日本列島の写真を見ると、東京-名古屋-大阪間の地域がひときわ煌々と輝いているのが見て取れる。
また、筆者は1時間程度の通勤圏をGTMA(Greater Tokyo Metropolitan Area)と定義しているが、そこには日本の人口の3割程度が住み、日本のGDPとPFA(Personal Financial Asset:個人金融資産)の4割程度が集中している。都市化が世界中で進んでいるというのは周知の事実だ。しかし、これほどの巨大な都市圏が出現するとはだれも想像していなかったかもしれない。
東海道メガロポリスとGTMAの形成を促進したのは交通システムの貢献が大きいであろう。20世紀の初頭、それまでの折衷主義のアンチテーゼとして機能主義が主張された。様式よりも機能を重視すべきだという主張である。その際、都市の機能は「住む」「働く」「遊ぶ」という考えが提示された。しかし、オーストラリアの首都キャンベラなどの経験をもとに、この3つでは魅力的な都市はデザインできないということが明白になった。その問題に答える模索が行われた。20世紀の半ば頃、都市の機能はもっとあるのではないかということが言われ、日本では磯崎新が「出会う」、黒川紀章が「移動する」を都市の機能に加えるべきだと主張した。その後、「出会う」は大阪万博の「出会いの広場」で見事に失敗した。一つのパビリオンから次のパビリオンに急ぐ多くの入園者はその広場を対角線に突っ切るだけで、人と人は出会わなかったのである。
しかし、黒川紀章の主張した「移動する」は確かに都市の重要な機能であるかもしれない。東海道メガロポリスでは東海道新幹線、GTMAではJR山手線がその機能を担っているのではないだろうか。東海道新幹線は汽車ではなく、それまでに世界に存在していなかった、すべての車両にモーターが付いている高速電車システムという技術革新であったが、JR山手線はとりわけ新しい技術ではなかった。しかし、哲学的と言ってもいい発想の転換であった。すなわち、CBD(Central Business District)という都市活動の中核を「点」から「円」に拡大したのである。それによって、東京は物理的なサイズがそれほど大きくないにもかかわらず、都市の活動の多様性と密度が拡大したのである。その意味で、世界の都市デザインにおける成功例の一つであろう。
東京のCBDは明治以降、東京駅と皇居の間の丸の内地区であった。その後、郊外に拡大していく通勤客を対象にした私鉄が勃興した際、すべての私鉄は東京駅に乗り入れることを望んだのである。それに対して、当時の鉄道省は、お雇い外国人であったドイツ人技師が提案し、お蔵入りになっていた、皇居の周りにある東京駅、東北本線の上野駅、中央本線の新宿駅、東海道本線の品川駅という当時の既存の駅を環状に結んだ山手線の案を思い出し、私鉄各社に、東京駅ではなく、この環状線のどこかに接続するように命じたのである。それによって、既存の駅に加えて、新たに池袋、渋谷、大崎などの駅が追加のモーダルチェンジ・ポイント、すなわち、国鉄と私鉄との乗換駅として出現した。そして、それらの駅の周辺が経済活動密度の高い拠点となったのである。すなわち、普通は都市に一つしかないCBDが沢山できたことになった。
山手線は一周が1時間である。ということは目的の駅まで30分以内に行けるということであり、心理的に許容できる範囲である。しかも環状であるから終点がなく、乗降客数も確保しやすい。ちなみにボストンは20世紀初頭には最高の地下鉄網を持っていたが、その後1960年代まで衰退を続けていた。末端の支線の乗降客が確保できなくなり廃止になるとその先につながっている本線の客も減るという悪循環に陥っていたのだ。その後回復基調にあったが、井桁状にCBDで交差する4つのラインのうち、ハーバード・スクエアを終点としていたレッド・ラインを延長し、環状線とした。自動車中心の都市化を進めてきたアメリカの都市としては珍しい展開だ。しかし、東京のようなモーダルチェンジ・ポイントとしての機能はないという意味で都市の展開は違うようだ。
このような「移動する」という機能の大発展が都市にもたらしているのが大気汚染である。これはどこの大都市でも大問題だ。東京に比較的その問題が少ないのは、1970年代に排ガス規制を進めたこともあるが、基本的にはモーダル・チェンジがうまく機能するマス・トランスポーテーションが発達していることの貢献度が高いからだろう。しかし、ドア・トゥ・ドアの便利さはなく、通勤地獄の抜本的解消もむつかしい。しかも、今の規模のGTMAにとっては環状線が円ではなく点に近くなっているという制約が出てきている。
今後は都市の大気汚染の対策として電気自動車を推進するのであろうが、「電気自動車」ではなく、からEPMS(Electric People Mover System)ととらえるべきであろう。自動車の概念にとらわれた、現在の自動車中心の交通システムにおける道路網を前提にするのではなく、もっと自由なライト・オブ・ウェイを活用する交通システムになるであろう。それによって、ドア・トゥ・ドアの利点と、マス・トランスポーテーションの便利さとを連結し、しかも、排気ガスのない都市内、都市間交通網が出来上がってくるであろう。新たなモーダルチェンジ・ポイントも出現し、そこで出来上がる都市の活動ミックスも大きく変わるかもしれない。そのようなことを組み込んだ都市デザインの革新が求められている。
モータリゼーションがかつてアメリカにおいてCBDの衰退とドーナツ現象を引き起こしたことは記憶に新しい。ここで言うEPMSはそれを避けることができるのであり、そのようにEPMSの展開をもとに都市の中心部であるCBDの変革をデザインし、それらの多くのCBDが東京の環状線とは異なった形態の拡大可能なネットワークを組むように発展を続けていくように仕組むことで、広域経済活動の健全な拡大を進めることができるであろう。
普遍性ある新たな指標体系
中国の大都市、とりわけ北京市の大気汚染の状況は近年盛んに報道されている。市内の走行車数の制限など対症療法的、短期的施策は適宜実施され、それなりの効果を上げているようだが、最終的な解決にはならない。排気ガスを減少させるためであろうが、長期的にEVへの転換を強力に推し進める政府方針の発表が最近あったが、それが排気ガスの減少という真の成果を上げるには20~30年はかかるであろう。
EV自体は排気ガスを出さないが、充電をしないといけない。電力需要は増大させるが、一方では電力供給のかなりの部分を占める石炭火力発電を減らしていかないといけない。しかしそれを代替する主要手段としての自然エネルギーは供給量が常に変動する課題を抱えている。需要側も変動するので、その間を絶え間なく微調整する必要がある。そのため蓄電装置が不可欠だが、それを含めて経済的に妥当な価格で提供できる電力供給システムを構築するには、物事の展開のスピードの速い中国でも今後20年はかかるに違いない。
システムはある日突然完成するのではなく、その間、状況はちょっとずつ良くしていくものである。しかし、それは直線的な改善ではなく、いろいろ紆余曲折を経ていくことになるであろう。その間、政府も国民も短期的な諸問題の対策のための議論にかまけて長期的に目指す方向を見失わないようにする必要がある。それにはどうしたらいいだろうか。その一つの答えがグリーン都市環境指標を確立することである。
その指標体系は為政者である政府も生活者である国民も共有でき、毎年、その指標に沿ったデータが公開されることによってその進捗状況を確認できるものであり、また、指標間のバランス、進捗状況など、都市間の比較が可能になり、健全な都市間競争の醸成と、各都市の置かれた歴史、風土、自然環境などの特質に応じた重点施策の立案のための情報源になるはずである。そのような発想と視点をもとに本書〈中国都市総合発展指標〉の指標体系の開発が行われた。
都市環境を評価するための指標は数多く抽出することが可能であり、実際数多く存在し、使われているが、それをすべて取り入れるのではなく、全体のバランスや網羅性を失わないようにしながら、指標全体の数を可能な限り少なくすることを目指した。その結果、全体の指標の数を27個に集約した。それをただ羅列するのではなく、三層構造に組み立てた。すなわち、大項目指標3、中項目指標3、小項目指標3の3×3×3で27になる。一般の生活者が大項目指標の三つを記憶することは可能なはずだ。もっと関心のある人は3×3=9、すなわち、中項目指標の九つを記憶すればより一層この指標体系の理解が進むであろう。そして、専門家は27項目のすべてを記憶し、それぞれの改善を追求するという発想である。
大項目指標は環境、社会、経済の三つから成り立っている。それぞれを三つに分けたのが中項目指標であり、それをまた三つに分け、一層具体的にしたのが小項目指標である。当然のことながら、統計を担当する部署はこれまでそのような視点からデータを取ってきたわけではないので、基本的な三層構造と方向を生かしながら、既存のデータのありようや収集可能性とつきあわせ、大・中・小の指標は修正された。
基本的な思想として、経済活動の発展と都市生活者の生活基盤の質の向上をバランスさせる視点を重視している。生活者それぞれが自分の住んでいる都市がどのように経済を発展させ、雇用基盤を拡充しながら同時に生活環境を改善していくのだろうか、ということに積極的に関心を持つこと。これが都市行政の担当者にフィードバックされ、結果として都市環境の長期的な方向への持続力を維持することになるはずだ。
そのためには指標は専門家だけのものではなく、生活者も容易に理解し、記憶でき、自分の住んでいる地域が将来どうなっていくのかに関心の持てるものにするよう留意した。生活者は大項目指標の示す将来展開に常に注目することで、細部は別として大枠の方向は理解できるであろう。より細かい中指標、小指標がどうなっているかについても年ごとの生活実感の変化を追うことで理解できるはずである。
もう一つ留意した重要な視点を挙げると、都市はそれぞれ独立ではなく、都市間ネットワークが出来上がっていることだ。そのような都市間のお互いの関係は大昔からあった。すなわち、都市と都市は相互依存の関係にあったのである。たとえば、「シルクロード」という表現を聞くと、我々は中央アジアの広大な砂漠をラクダの隊商を組んで一本道をゆっくり進む姿を思い浮かべがちである。しかし実際は、商人たちはシルクロードの起点から終点まで歩んだのではない。沢山の交易都市がきめ細かい道路網というネットワークを組んでいて、そのような都市と都市をつなぐ形で行き来し、商品を売買し、あるいは受け渡していたのである。
それが、近年の交通機関の発達によって、そのネットワークが一層強化され、メガロポリスと呼ばれるような連携と一体化が進んだのである。そのような文脈の中でそれぞれの都市を捉えることに着目している。それは都市間のインターリンケージ(相互連鎖)である。そのインターリンケージが国境を超えて展開する状況を、グローバリゼーションと我々は呼ぶのである。
たとえば、都心に近い空港である虹橋、金浦、羽田の間をシャトルと呼んでいい頻度の航空便が提供される時代であり、それによって、上海、ソウル、東京の間のインターリンケージは増していく。このような現象のポジティブな展開を醸成することが都市の活力を増すのは間違いない。ちなみに、この三つの都市および周辺に住む人口は1億人を超えており、その多くは豊かな生活者であり、世界でも有数の経済活動の活発な地域である。
このような都市のインターリンケージはすなわち、1)都市圏内の中核と周辺、2)都市圏と都市圏、3)都市圏と世界、の三つの様相に分けることができる。そして、今回の都市指標はこの三つのどれかに関係しているといえる。たとえば、「都市農村共生」、「文化施設」、「生活品質」は1)に、「イノベーション・起業」、「広域輻射力」、「ビジネス環境」は2)に、「開放度」、「人的交流」、「広域インフラ」は3)に関係が深いということができるだろう。
それぞれの大都市の行政官はこのような三つの方向を睨みながら、都市環境を改善していくために重点施策を立案し実施していくことが期待される。そして、それは都市間の競争であると同時に相互にメリットのある連携を確認し、拡大していくことであり、それが世界の都市との連携まで広がっていくという実績を積んでいけば、〈中国都市総合発展指標〉は世界に対して普遍性のある新たな指標体系として、認知されていくことになるであろう。
1.都市は国の一部であり、また、国全体の代表でもある。東京、横浜と言えば日本の象徴であり、北京や上海は中国の代名詞でもある。代表的な大都市は、歴史的にも地理的にも、それらが栄えた時代の代表として評価される。
私の手元には、「清明上河図」(Riverside Scene on Qingming Festival) がある。最も好きな絵の一つである。現在、私は中国政府の環境国際協力委員会の委員を務めており、中国の様々な情報に接する機会が多いが、以前から中国オタクであり、政治や経済はもとより、文化、学問などあらゆる分野の中国の歴史探求が趣味である。上記の絵を評価するのも、そこに示されている宋の都である開封市の経済的な繁栄や、それを支える人々の仕事と遊びが描かれていることにある。この時代から中国の本格的な商工業が成立したと考えており、南宋時代も含めた300年が中国資本主義のスタートと捉えている。そして、その象徴がこの絵に込められている。最も関心を寄せる歴史上の人物は、この宋の時代に変革者として現れ、政治と経済の改革に全力を尽くした王安石である。彼の目指したところは、大商人・大地主などの利益を制限して農民や中小の商人を保護する、そして、経済活動全体を活性化し、政府も納税額を確保しようというものである。中国の長い歴史の中でも特筆すべき新たな経済思想に裏付けられた改革であった。当然のごとく既得権を有するグループからの反対は強く、道半ばにして改革は頓挫したが、こうした挑戦がある程度行われたこと自体が、宋という時代の特徴をなしている。
開封市、杭州市という二つの首都は、この時代の世界的な大都市であり、経済の中心としてよく機能している。日本でも、初めて武士による政治と経済のリーダーとなった平清盛は、この宋という国と首都の機能を高く評価していた。
2.生産、流通、消費の機能を備えた都市の成立は、中国がヨーロッパに先行した。それは高い経済力とセットであり、世界一の経済力と高度な技術力(火薬、羅針盤、活版印刷の発明)が裏づけとなった。宋、元の時代を経て、明の初期には、鄭和率いる大船団がアフリカにまで達した。優れた工学技術力がその基礎にあった。しかし、その後の、事実上の鎖国政策、片や欧州では保険などの金融システムや株式資本といった文科系技術の導入があり、その結果として欧州、そして遅れてきたアメリカによる世界支配の時代に入った。
3.中国が長期の停滞から脱却したのは、1980年頃からであり、改革開放路線の導入による。北京、上海は当然のこととして、天津、武漢、重慶、瀋陽、広州、仏山、長春などの工業都市、鞍山、撫順、大慶などの鉱業都市の大都市化が進んだ。中国は、「世界の工場」として成長し、重要な労働力として農村部から都市部への人口移動が行われた。そうした地域では、当初、一部地区のスラム化現象が見られたが、徐々に生活環境が整備され、新たに形成された中産階級の生活の舞台として、効率の良い都市となっていった。例外は香港であり、連合王国の監督の下、1960年頃からアジアの金融のハブとして成長を遂げいち早くアジアを代表する大都市となった。
4.現在も、中国は大都市の起爆力を維持しながら経済的な力を増しつつある。その力は、いくつかの源を有する。まず①「世界の工場」であり続けることである。経済成長に伴う賃金水準の急激な上昇により「安かろう悪かろう」の製品作りの時代は終わり、ハイテクを用いたレベルの高い工業製品の製造に転換しつつある。現実に、時代の最先端を行く再生可能エネルギーの製品は、ソーラーパネルを筆頭に中国製品が世界の市場を席巻している。質は日本製と変わらず、値段が圧倒的に安いのである。これは、スマホ生産でも同じである。②ついで、BATと称されるGAFAに匹敵する企業の躍進である。百度、阿里巴巴、騰訊に加え、ネクストBATとしてTMDの成長も見られ、知識集約型の都市の成長も見られる。③AI、IoT分野を中心に大学での研究も世界のトップレベルを走っている。清華大学を始め、北京大学、天津大学、復旦大学、中国科学技術大学、武漢大学、湖南大学などが、大都市区域の中心に位置し、それぞれの都市に活力を与えている。④ユニコーン企業の大都市での誕生と成長が顕著なことも注目される。ユニコーン企業の数では、世界のトップをアメリカと競っている。杭州、北京、上海、深圳などの大都市に更なる魅力と活力を加えている。
5.大都市が抱える課題もまた多い。中国が悩まされている問題の一つに環境汚染がある。報道されることの多い大気汚染については、いまだ不十分だが徐々に改善されつつある。習近平主席のリーダーシップによるものであろう規制が急速に強化された成果だと思われる。水質の分野でも大気汚染と同様にEU並みの厳しい基準が施行されている。しかし、いずれもいまだ改善は不十分であり、全く手のついていない土壌汚染対策を含め一層の対策の充実が必要である。また、廃棄物については都市廃棄物と産業廃棄物を総合的に律する法体系がないことから統計が乏しく、現時点での都市ごとの評価は困難である。衛生面からも課題がある。日本では1900年に廃棄物処理の最初の法制化が行われたが、これの狙いは、廃棄物の散乱や不適正な処理に伴うハエや蚊などの衛生害虫の発生を抑制し、コレラ、ペストなどの感染症の拡大を防ぐことにあった。中国での廃棄物処理の一元的な管理制度の実現が待たれる。
6.衛生といえば、今回のCOVID-19の拡散といった事態を今後未然に防ぐ、あるいは拡大を防ぐ機能は極めて重要である。医師、病院の数の確保、あるいは野味市場(食用の野菜動物を扱う市場)の整備整頓など具体的対策は今後の検討が待たれるが、感染症の発生を未然に防止する、あるいは最小限にとどめるといった衛生状態の改善策は、今後の中国大都市の重要な課題である。
7.文化面も評価を加えたい。私の中国の知り合いで日本を頻繁に訪れる友人は、時間があれば、京都や奈良を訪れる。そして、かつての唐の長安を偲び、唐招提寺では鑑真和上を偲んでいる。中国の大都市に歴史地域の保全と復元を強く希望するものである。
8.本当に人が住みたくなる、そして住んで楽しいと思える場所はどこなのだろうか。それは、その人が自分の持っている才能の全てを出せると実感するところだと考える。人の幸せが何かはそれぞれに異なるが、種田山頭火が詠う「山あれば山を観る 雨の日は雨を聴く 春夏秋冬 あしたもよろし ゆふべもよろし すなほに咲いて白い花なり」という、出逢うもの全て受け入れるという気持ちと、A.Einsteinの言う”Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. “に代表される積極的、能動的な気持ちの双方が、時にばらばらに、また同時に、実現できる環境が必要である。人の幸せは、周囲の人の言動や評価にあまり影響されてはいけないし、またあまり断絶していることも良くない。その微妙な線の幅を自らつかんで展望を開きうる環境とは何か、どこか、という難しい問題がある。各人が持つやわらかな頭脳と心意気を大いに伸ばして活躍したい、そんな望みを持つ彼ら、彼女らが、喜んで住み、働ける魅力ある都市づくりを進めていきたいものである。自然環境や人情に溢れた都市を造っていきたい。周牧之教授が中心になって取りまとめられた〈中国都市総合発展指標〉は、以上に述べた私の思考の迷い道に新しい道標を与えてくれるものと期待している。
1.未来都市の形
未来都市とはどのような都市像を思い描くであろうか。エベネザー・ハワードは1898年に理想的な都市として、住宅が公園や森に囲まれた緑豊かな田園都市を提唱した。また、ル・コルビジェは「輝く都市」(1930年)の中で、林立する超高層ビル群とそれによって生み出されたオープンスペースによる都市像を示した。全く異なる都市像ではあるが、どちらも当時の急激な都市化によって生じた都市問題を解決する手法として提案された。それから1世紀近くが経過し、当時提唱された都市像は、現在の大都市の都心部や郊外都市などでその片鱗をうかがうことができる。
20世紀の都市では、産業革命以降の様々な科学技術の進歩が都市の生産性を大幅に向上させ、急激な人口増加や都市部への人口流入が続いた。特に自動車の出現は、人々の日常生活を大きく変化させ、緑豊かな郊外に向けての住宅開発が豊かな都市生活を実現させた。しかし、一方で郊外への無秩序なスプロールは、都市構造にも大きな影響を与えた。過度に自動車に依存した都市では、道路渋滞や交通事故などの交通問題が大きな社会問題として捉えられ、現在でもその解決策が講じられ続けている。その対策はかなり早い段階で議論され、例えば近隣住区論(1924年)では、自動車を前提とした安全な居住地区の整備が提案された。その後も自動車と居住環境の望ましい関係を模索する様々な都市像が提案され、世界各地で多くのモデル地区が出現している。
21世紀に入り、我が国の人口増加はピークに達し、人口減少時代を迎えている。また、環境問題が地球規模で議論されるようになり、理想的な都市像にも変化が見られる。特に、現在の都市政策に大きな影響を与えているのは、1987年に国連のブルントラント報告のなかで推奨された持続可能な開発の都市モデルである。過度な自動車社会から脱却し、魅力的な都心を形成し、公共交通や徒歩で暮らすことができるコンパクトなまちづくりが進行している。
2.コンパクトシティ政策
コンパクトシティは行き過ぎた自動車社会に対して、人と環境にやさしい歩いて暮らせる持続可能な都市モデルとして注目を集めている。その定義は様々であるが、総じて以下のような要素を含んだ都市を示す。
(密度)一定以上の人口密度を保ち、市街地の効率性を高める。
(空間)一定エリアに機能集約させ、街中の賑わいを創出する。
(移動)公共交通を活用して、歩いて暮らせる街をつくる。
(資源)既存の資源を上手に活用し、歴史やコミュニティを大切にする。
一方で、日本におけるコンパクトシティは少し異なる文脈のなかで必要性が語られている。その一つは急激に訪れる人口減少社会への対応である。2050年までに総人口の23%が減少すると予測されており、20世紀の人口増加期に拡大した市街地を上手に縮退させて持続可能にすることが、都市行政として急務とされている。超高齢化社会で生産年齢人口が減少し、都市インフラの維持管理に関する財政負担は予想以上に大きい。
3.スマートシティ
一方で、科学技術を活用した新しいまちづくりも模索されている。その一つがスマートシティであり、ICT等の新技術を活用しつつ、全体最適化が図られる持続可能な都市または地区と定義できる。
もともとスマートシティの概念は、電力の流れを最適化するスマートグリッドのように、エネルギーの効率利用の視点から、2010年頃から民間企業を中心に広がり始めた。特定の分野特化型の取り組みからスタートしたが、近年では環境、交通、エネルギー、通信など分野横断型の取り組みが増えている。国家主導の「Smart Nation Singapore」や、官民連携としてカナダ・トロントの都市開発プロジェクト「Sidewalk Toronto」など多くの事例が出現している。
スマートシティとコンパクトシティは何が異なるのか? 2つの都市モデルを多様な視点から比べてみるとその特徴が見えてくる。まず、コンパクトシティは都市空間を対象としているのに対して、スマートシティは主として情報を対象としている。前者は現実空間に実在するため見ることができるが、後者は仮想空間での情報の動きなので目に見えない。コンパクトシティは計画・マネジメントを通して都市空間の縮退を目指すのに対して、スマートシティは情報技術(Connected Technology)を駆使して、市場の拡張がベースとなっている。どちらも持続可能な社会を目指す点では一致するが、その方法等は大きく異なっている。
4.新しい都市像に向けて
コンパクトシティもスマートシティにも共通する指標として「シェア」がある。市街地を一定のエリアに集約して、都市空間を上手に共有(シェア)するのがコンパクトシティである。人口密度を一定のレベルに保つことは、居住空間の効率的な利用を促していると解釈できる。また、道路空間も私的なマイカーが占有するのでなく、バスや路面電車などの公共交通を利用することで移動空間を効率的にシェアすることになる。つまり、コンパクトシティではシェアによって居住や移動など様々な都市活動の効率性を高めている。
スマートシティでは情報を対象に、ICT技術を活用して情報をシェアすることで、都市活動の効率性を上げる。エリアレベルでのエネルギーの相互利用や分野横断的な取り組みも、異なる業態の情報シェアがカギとなっている。例えば、移動時の情報シェアはMaaS(Mobility as a Service)のような統合型交通サービスを可能とする。
換言すると空間シェアをすすめるコンパクトシティと、情報シェアをすすめるスマートシティの融合が、新しい都市像を生み出していく。歩いて暮らせる範囲にコンパクトな都市空間が形作られ、その空間は定時性を確保した魅力的な公共交通がつないでいく。集約エリアの周辺には緑豊かな市街地や田園風景が広がり、自動運転車がエリアの拠点までの足となる。移動は統合的な交通サービスの中で行われ、様々な交通手段を上手にシェアすることで、交通インフラ全体の効率化と環境負荷低減に寄与する。平常時も非常時もシームレスな情報ネットワークで、都市生活の安全性と快適性を確保する。こんな未来都市の実現がもう近くまで来ているのかもしれない。
中国国家発展改革委員会発展計画司と雲河都市研究院が共同研究制作した〈中国都市総合発展指標〉は、中国における都市の発展状況を全く新しい視点でまとめ上げた報告書であり、正に総合的で発展的な都市評価指標である。これまでのように経済発展の成果を見るだけでは、都市の発展を語るには十分ではない。その意味では社会、環境の指標が欠けていれば、たとえ経済面の指標が多数あったとしても、都市を総合的に評価できたとは言えない。
都市の発展には、空間における均衡発展の理念と原則の確立が欠かせない。空間における均衡発展とは、都市という空間の中で、人口(社会)、経済、環境資源という三者間の均衡を実現することである。都市空間における均衡発展の理念と原則の確立は、人間と自然との調和のとれた都市化をはかるために重要な意義を持つ。
現在、一部地域における生態環境の悪化は、当該都市の人口規模や生活水準を向上させるための経済開発が、当該地の環境資源のキャパシティを超え、都市空間における均衡が崩れたゆえである。経済発展のみを優先させるあまり、「発展権」に基づいた経済開発が横行し、生態環境の悪化をもたらしている。
生態環境が一旦破壊されると、退耕還林(耕作を中止し耕地を元の林に戻す)、退牧還草(放牧をやめ、草地を元に戻す)、水土流失(土壌の流失)対策、風砂被害対策、砂漠化防止対策などの「生態環境対策事業」に膨大な資金を投じなければならない。また、渇水や環境悪化が人々の生活に影響を及ぼすたびに、遠隔地送水事業、汚染対策事業に奔走することになる。
実際、中国の一部の都市では現在、「都市病」が蔓延している。都心部の過密化、住宅価格の高騰、著しい交通渋滞、充満するスモッグなどに苦しめられている。
〈中国都市総合発展指標〉は、環境、社会、経済の3つの視野で都市の発展を評価し、都市空間における均衡発展を重視する真の意味での都市の総合発展評価である。このような都市発展評価は、まさしく科学的かつ包括的な評価であり、中国の都市の持続的な発展に大きく寄与する。
これまでの30年間、中国では数億の人口が農村から都市に流入した。今後さらに数億の人口が都市に流入するであろう。これは今後中国が直面する最大の圧力である。その人口大移動によって最も影響を受けるのは生態環境である。その意味では中国のこれからの都市発展は、煌めく星空、美しい河川、朗らかな鳥の声を犠牲にする経済規模の拡大や道路の拡張、高層ビルの林立であってはならない。
中国の都市は、生態文明の理念を堅持し、生態環境を重視する都市発展を進めなければならない。土地、水、エネルギー等の資源を節約し、自然へのダメージを最小限に抑えなければならない。生態安全を重視し、森林・湖沼・湿地などの環境生態空間の比重を増やし、さらには汚染物質の排出総量を減らすことも肝要である。
〈中国都市総合発展指標〉は、応用可能な環境、社会、経済指標を体系的に示している。各都市は自らの指標を精査し、どの分野で滞りがあるかを見出し、改善に向けて努力すべきである。〈中国都市総合発展指標〉はただの評価指標ではなく、都市の今後進むべき道を指し示すものでもある。
世界は「フラットではない」。アメリカ、EU、日本を代表とする先進国は世界経済の中で主導的な地位を占め、大多数の発展途上国は従属的地位にある。こうした「不均衡」は、一国の中でも見られる。世界銀行の『2009年世界発展報告』は、都市を単位に地域発展の差異を図解し、その驚くべき格差を示した。例えば、東京大都市圏は世界最大の“都市”で、人口は3,800万人にも達し、3.6%の国土面積で日本の32.3%のGDPを生み出している。また日本全国の上場企業の58.2%、科学技術者の68.7 %、そして特許取得数の60.6%がこの大都市圏に集中している。大都市は内外から人材、資金、企業を吸収し、急激に膨張している。これに対して他の地方都市の発展は相対的に不十分で、都市間の格差は時に国家間の格差さえ超える勢いで広がっている。
この意味では、中国もまた「フラットではない」。
中国では「黒河・騰衝線(胡煥庸線)」 東南側に位置する43%の国土に、なんと94%の人口が集中している。これに対して、国土の57%に当たる西北地域にはわずか6%の人しか住んでいない。これが中国の空間構造の最も基本的な特徴である。
また、「胡煥庸線」東南側でさえ、内部の差異は顕著で、都市と農村、そして都市間においてその発展水準の格差は極めて大きい。
2016年、上海の常住人口は2,419万人で1人当たりGDPは約11.4万元であったのに、安徽省の省都合肥の常住人口が786万人で1人当たりGDPは約8万元、貴州省の省都貴陽の常住人口は469万人で1人当たりGDPは僅か約6.8万元である。3都市の人口規模および1人当たりGDPの格差は極めて大きい。しかし、これは省都以上の中心都市の比較であり、中心都市とその他の地方都市とを比較すると、その格差は尚、著しい。
もちろん、GDPという単一的な指標による描写だけでは人を納得させることはなかなか難しい。願わくば、都市発展の実態をしっかり反映できる総合的な指標が必要である。数多くの領域の差異を整理し、より総合的に都市の差異を反映させる指標であることが望ましい。こうした指標は、都市の現状を知り、ビジョンを描き、そして公共政策を導入することに役立つ。
中国国家発展改革委員会発展計画司と雲河都市研究院が協力して開発した〈中国都市総合発展指標〉は、まさしく先駆的な都市総合指標である。
同指標は、都市発展の国際的経験に鑑み、環境、社会、経済を3つの主軸に都市を評価する。それによって中国の都市をより環境に優しく、彩りある社会につなげ、イノベーティブな産業活動を促せるよう期待したい。
〈中国都市総合発展指標〉は指標を用いて、都市発展の水準を評価し、データを活用して都市発展の方向を探る目的で開発された。都市発展は、動態的過程で、それに影響が及ぶ要素はきわめて複雑であり、さまざまな評価手法が有り得る。同指標はこれに一石を投じるものである。
今後、進む情報化が「不均衡」をさらに複雑化させるだろう。ビックデータや人口知能など現代技術が都市発展構造に与える影響もさらに広がる。
中心都市は、最新技術開発と応用における優位性でその集約趨勢はさらに強まるであろう。中小都市も、情報技術を利用し、その低コスト空間における優位性を活かせる道を見つけられるよう願いたい。
その意味では、〈中国都市総合発展指標〉が、都市発展における変化に対してリアリティのある追跡を行うことが重要な意味を持つ。
中国では将来、個々の都市の単独発展よりは、都市が連携するメガロポリス的な発展がメインになるだろう。情報ネットワークと交通インフラ整備によって、都市間におけるさまざまな機能の共有が進んでいく。〈中国都市総合発展指標〉の評価対象は個々の都市より、メガロポリスへと重点を移していくだろう。
都市の発展メカニズムの変化に応じて、〈中国都市総合発展指標〉も進化していく。
都市化は、過去40年における中国経済社会高速発展の原動力の一つである。なぜなら都市化の本質は構造改革であり、都市と地域の制約を超え、人口の流動性と再配置が促されるからである。改革開放以来、中国は人類史上最もハイスピードな都市化を経験した。40年間で、中国の都市化率は年平均1%ポイント向上してきた。その結果、現在、都市化率は57.4%に達し、都市の常住人口は7.9億人に膨れ上がった。
2017年に開催した中国共産党第19回全国代表大会は、中国がすでに高度成長からハイクオリティな発展にシフトする段階にあると宣言した。ハイクオリティな発展には、ハイクオリティな都市化と都市発展が必要である。その意味では今後なお、都市化は中国のさらなる発展の重要なエンジンとなる。
1.問題と挑戦
中国の急速な都市化の中で、軽視できない問題も数多く累積している。
(1)数多くの都市常住人口が市民化されず、都市内部で二元構造が発生
目下、中国では農村から都市へ移動した人口が約2.7億人に達し、また戸籍の移動を伴わない都市間移動の人口も8,000万人以上いる。問題なのは、戸籍制度が障害となり、こうした人々が居住都市で市民待遇を受けられず、単なる労働力として利用され、社会的に公平な福祉の待遇を受けられないまま差別されていることである。彼らは事実上、中国の都市発展に多大な犠牲を強いられている。都市繁栄の背後には、こうした人々の辛酸、犠牲、そして諦めがある。非戸籍住民にとって都市には市民感覚が持てず、生活の安定感を欠いている。
(2)拡がる都市空間の非効率利用
中国の多くの都市では、数多くの工業園区、新区そしてニューシティが計画されている。過剰な開発がゴーストタウン、旧市街地の空洞化などの問題をもたらしている。これまで「土地の都市化が人口の都市化」より進んだことで、都市の土地利用率を低下させてきた。こうした傾向をもたらした地方財政における土地売買への依存などについて真剣に改革していく必要がある。
(3)過剰なインフラ整備
野心的な都市計画は往々にして過大なインフラ投資を生む。過剰なインフラ整備は、現在、中国の地方政府の債務負担を増大させる大きな要因となっている。
(4)都市の開放性と寛容性の欠如
中国では大規模人口のマネージメントに対する憂慮から、都市の人口規模が大きくなればなるほど開放性と寛容性が低くなる現象がある。このような開放性と寛容性を犠牲にするような都市のマネージメントは、都市の活力と創造力を弱めている。
(5)都市計画における先見性の欠如
中国では都市計画における先見性が欠如している。人口予測は過小であったり過大であったりする場合が多く、都市建設はそれに翻弄されている。背後には、都市発展のメカニズムに対する理解のなさがある。
(6)産業構造転換の遅れ
中国では、計画経済時代に作り上げられた工業都市と資源開発型都市が多数ある。これらの都市では産業構造の転換が遅れ、産業力の低下に伴い、人口が外部へと流出し、衰退の危機にさらされている。
2.方向性と施策
中国の都市化と都市発展のクオリティの向上をはかるには、下記の方向性と施策が必要だ。
(1)農村からの移動人口の市民化
中国共産党第19回全国代表大会では、農村からの移動人口の市民化の加速を明確に求めた。すべての都市がこの施策に基づき、すでに都市で安定して就業し暮らしている農村からの移動人口に対し、都市戸籍登録をするかしないかを自主的に選ぶ権利を与えるべきである。
人口流動が主として経済の遅れた地域から経済発展地域へと進むことから、移動人口の市民化は、中国経済の空間分布と人口の空間分布の最適化をはかることから始まる。ゆえに数多くの農村人口が都市に移動し、多彩な現代文明の薫陶を受け、子女の教育条件が改善されれば、中国人口の質的向上と現代化とに大いに役立つであろう。
(2)都市産業の強化
都市は絶えまない産業高度化を通して持続発展を可能とする。ただし、これは政府が直接産業に投資することを意味するものではない。政府がなすべきことは、インフラ整備や人材育成を含むビジネス環境の整備である。
(3)都市マネージメントの改善
都市社会は市民社会である。この意味では、都市マネージメントに住民参画を促すべきである。これは都市の開放性と寛容性そして吸引力の根源となる。現在、世界で最も活力があり、イノベーティブな都市はすべて開放的で寛容性のある都市である。中国も例外ではない。なぜイノベーティブな人材と企業が深圳に集積するかというと、深圳が移民都市であり、中国の他の都市と比べて、より開放性と寛容性を備えているからである。
(4)メガロポリス主体の都市空間作り
メガロポリスを主体とした大中小都市を協調発展させる都市空間作りを進めるべきである。そのために都市計画の理念、制度、方法の改革を加速しなければならない。メガロポリスのフレームワークの中で、個々の都市の経済産業、インフラ整備、生態保護、社会生活などを総合的にとらえ、最適化を図るべきである。
(5)新たな都市インフラ整備融資制度
都市インフラ整備は膨大な投資を必要とする。現在、中国の多くの都市ではインフラ整備における融資困難と、都市の債務リスクの双方を抱えている。その原因の一つは、都市インフラ建設の規模が過大で、投資規模と債務規模を拡大したことにある。もう一つは、有効な投融資メカニズムの欠如である。ゆえに、都市インフラ整備における新しい投融資制度の開発が必須である。
(6)都市建築の品質向上
中国は40年間で都市化率を40%引き上げた。各都市で建築物が雨後の筍のように立ち並んでいる。世界でも例を見ない巨大な建設ラッシュが中国で起こっている。しかし現在、建築物の品質問題も露呈している。ゆえに中国は都市建築の品質向上を急がなければならない。建築設計と工事標準を迅速に改め、建築物の耐久年数を上げ、低炭素かつ省エネを標準とすべきである。
3.〈中国都市総合発展指標〉の意義
上述したように、都市化と都市発展のクオリティは極めて総合的な概念である。この問題に取り掛かるにあたり、私たち中国国家発展改革委員会発展計画司は東京経済大学の周牧之教授が率いる雲河都市研究院と協力し、〈中国都市総合発展指標〉を開発した。中国の地級市以上の298都市を統一された指標システムによって評価し、総合的に都市発展クオリティをはかることができた。
もちろん、指標体系自身も都市評価を通じて議論し改善し続けるべきであろう。最も大切なのは、こうした評価の継続である。それによって、都市の発展クオリティを年毎にシステマティックに観測できると同時に、時間軸に沿って都市発展の歴史も記録できる。
過去20年間、中国の都市化は急速に進み、多くの人々が都市へ移住した。大規模なインフラ整備により、都市の物理的なスケールは拡大の一途を辿った。新中国建国以来長い間遅れていた都市化が、ついに加速しはじめた。
都市が都市たる所以は、限られた空間に多様、複雑かつ豊富多彩な経済文化活動が存在することである。このように見ると、都市は密度で定義するべきである。
しかし今まで中国の都市化は、建成区(政府が定める都市的エリア)面積拡張の速度が都市人口増加の速度より速かった。つまり「人口の都市化よりも土地の都市化の方が先んじた」のである。
中国経済の規模は世界第2位であるが、1人当たりになると未だ低い水準に留まっている。同様に中国の都市も、面積は大きいものの、密度は小さい。
一つの原因は、中国の「都市」は広域行政区である。都市の行政エリアには市街地も郊外もさらに広大な農村までも含まれている。その意味では中国の「都市」の概念は海外一般の「都市」概念と同じではない。ゆえに行政の主導のもとで、農村エリアを侵食し、スプロール化しやすい。
「ローマは一日にして成らず」。都市エリアへの急激な拡張は、都市の環境、財政などにおける持続的な発展に大きな問題を突きつけているだけでなく、市民生活の向上や都市文化の育成が追いつかないことが多い。
中国の都市化は転換点にある。単なる都市エリアの拡大というやり方は、もはや持続不可能である。中央政府も地方政府も中国都市化の次のステップがどこに向かうか真剣に考えなければならない。
方向性は、中国経済発展にとって最も重要である。2014年3月16日、中国政府は「国家新型都市化計画(2014-2020年)」を発表した。この計画は中国都市化に、都市化法則の重視、人間本位、配置の最適化、生態文明、文化伝承などを明確に示した。
戦略的な方向性が示された以上は、実行可能な「指揮棒」が必要である。都市間競争に明確な項目およびゴールを示せば、都市のリーダーらは、行動しやすくなる。こうした観点から、周牧之教授と彼のチームは、中国国家発展改革委員会発展計画司のコミットメントのもとで、徹底的な調査、分析、比較を行い、〈中国都市総合発展指標〉として発表し、中国都市化の方向転換を導く科学的な指標システムを提供した。この指標はまさしく新型都市化を推し進める「指揮棒」である。
特に私は、「密度」を用いて中国の都市問題をとらえる同指標の斬新な知見に賛同している。
これまでの都市問題の政策議論では、いつも「大都市を発展させるか? 或いは中小都市を発展させるか?」の問題に翻弄されていた。〈中国都市総合発展指標〉は、大、中、小といったスケールで都市をとらえるだけではなく、その密度も問題にしている。
現在、中国の都市には多くの低密度都市空間が存在し、深刻なスプロール化が起こっている。したがって、大、中、小いずれの都市であっても、都市づくりにおいて「密度」を軸にすえていかなければならない。
初めて都市計画に関わったのは、10数年前のことであった。筆者はカナダから帰国し、北京市環境局に入局、当時中国国家建設部(省)大臣であった汪光焘先生が指揮した「北京都市計画と気象条件および大気汚染との関連性に関する調査」に加わった。その後、「北京および周辺五都市における2008年オリンピック大気質量保障措置の研究と制定」を取りまとめた。
工業化と都市化の急速な進展により、北京では人口が激増し、交通渋滞、水資源の枯渇、公共サービス供給不足と治安問題の頻発などで「都市病」が露呈した。2013年以来、PM2.5によるスモッグの頻発は、人びとの日常生活に一層甚大な被害を与えた。友人の中には汚染問題で国外に移住していった者もいた。
このとき、北京市門頭溝区の副区長を務めていた筆者は、都市大気汚染低減のため、再び都市計画に取り組むこととなった。エコシティの国際的な事例を参考に、北京市門頭溝区のために、経済発展、社会進歩、生活レベル、資源負荷、環境保護の5つの角度から、34項目の年度発展審査指標を作り、生態優先型経済発展を推し進める総合評価体系を制定した。
2014年末にはドイツを研究訪問し、都市計画専門家との交流セミナーで、彼等が詳しく述べていた「分散化」のドイツの都市発展モデルに、深い印象を受けた。これは、少数のメガロポリスに人口と経済活動が集中する中国の発展モデルとは明らかに異なっていた。
2016年に偶然の巡り合いで、幸運にも〈中国都市総合発展指標2016〉の出版発表会に参加し、著者の周牧之教授、徐林司長、そして各項目担当の専門家等と知り合った。その後続けて彼らに教えを受け、師としてまたよき友として、お付き合い頂いている。
周牧之教授は、工業化後発国は都市化において往々にして大都市発展モデルを歩む傾向があるとし、特に第二次世界大戦後、それが世界の趨勢となっていると、述べている。都市の集積効果は、経済発展効率を高め、豊富な都市生活をもたらす。とりわけ、メガロポリスのような大規模高密度の人口集積が、異なる知識と文化を背景とする人々の交流の利便性を高め、知識経済とサービス経済の生産効率を上げる。
都市病は「過密」がもたらしたものであるとされるのに対して、周牧之教授は「過密」の本質こそが問われるべきだと問題提起している。いわゆる「過密」の原因は都市インフラとマネジメント力の不足にあると言う。
周牧之教授は東京大都市圏を事例に「過密」問題を解説した。戦後、東京大都市圏が過密問題によりもたらされた大都市病に難儀し、いまの北京と近い発想で、工業や大学などの機能を制限した。しかしインフラ整備を進めた結果、都市圏の人口規模は拡大したにもかかわらず、いわゆる「都市病」は殆ど問題にされなくなった。これは北京の将来を考える際に非常に大切な示唆である。
周牧之教授は4年以上の時間をかけて、内外の専門家を集め、各国の都市化発展の経験と教訓とをもとに、都市発展を評価する指標作りを試みた。議論を重ね、環境、経済、社会の3つの軸から、〈中国都市総合発展指標〉を作り上げた。同指標体系は開放的で、時代の要求に応え、進化可能なシステムである。指標の数は2016年の133項目から、2017年には175項目へと増加した。
さらに、統計データだけではなく、最新の技術を駆使して衛星リモートセンシングデータやビックデータを大量に取り入れ、GIS技術を活用し、中国の地級市以上の全297都市の分析を行った。このような取り組みは中国では初めてのことである。よって中国の都市は、初めて環境、経済、社会の3つの軸で診断ができるようになった。様々な指標で都市のパフォーマンスが明らかになったことで、都市の課題と潜在力を浮かび上がらせ、より戦略的に都市の発展方向性を定められる。おそらくこれによって中国の都市計画レベルを一気に向上させることができるだろう。
〈中国都市総合発展指標〉から地域ごとの発展も評価できる。これによって、中国の東部、中部、西部地域の都市化進展の違いが確認できた。さらに同指標の2016年のメインレポート(『中国都市ランキング』第5章)では珠江デルタ、長江デルタ、京津冀、成渝の4つのメガロポリスの発展特徴を分析し、その将来性を予見した。同指標を活用し、中国の地域政策も大きく進化するだろう。
〈中国都市総合発展指標2017〉において北京は首都の優位性で連続2年総合ランキングの首位に立った。北京と天津2つのメガシティを中心に、京津冀というメガロポリスも形成された。
しかし京津冀は、その高密度人口集積に必要なインフラ整備、公共サービス、マネジメント力に欠け、水資源の不足、大気汚染や交通渋滞など都市病の困惑の中にある。
これに対して北京は、副都心建設を推進し、一部の行政機能などを通州などの周辺地域に移し、過密問題緩和を図ろうとしている。また、雄安新区の設立も、「分散化」の一環としてとらえられるだろう。
しかし、北京そして京津冀メガロポリスの発展にとっては、中心機能の強化も極めて大切である。「集中化」と「分散化」のバランスを如何に図るかが肝要である。そのために〈中国都市総合発展指標〉を活用し、これらの取り組みを常に評価し、軌道修正していくことが必要である。
1
田園都市運動の創始者、エベネザー・ハワード氏は1898年にある予言をした。それは、当時660万居住民を抱えていた英国ロンドンの人口が20%にまで縮小し、残りの80%がロンドン郊外のニュータウンに移住するというものであった。
予言は予言に帰し、現実は現実に帰する。ロンドン人口はハワードが述べたような軌跡を辿らずに増大の一途を辿り、1939年には860万人へと膨れ上がった。
人口の持続的な増大の一方で、「都市病」は日増しに悪化し、これに対応するため、イギリス政府は1940年、ロンドン市人口問題を預かる「パル委員会」による「パル報告」を発表、ロンドン中心地区の工業および人口の分散を主張した。イギリス政府は1946年、「新都市法」を発布し、ロンドン周辺で8つのニューシティ建設を主体とする新都市運動を立ち上げた。50年間の人口の流出を経て1988年に、ロンドンの人口はついに637万人になった。
何事もメリット、デメリットの両面性を持つものだ。新都市運動はロンドンを過密から「解放」したと同時に、「衰退」もさせた。「衰退」はロンドンにとって不都合であった。ロンドンは新都市運動を終結させ、復興運動を起こした。これは当然の帰結であろう。新都市運動は都市人口を分散させるのに対して、復興運動は人口の都市への回帰を促し、都市の活力を増大させた。人口データがこの効果を示している。2015年末になって、ロンドンの人口は854万人に達し、さらに、これを通勤圏人口規模にすると1,031万人に上った。
2
コースは違っても行きつく先は同じである。
ニューヨークでも私たちはこれに似た状況を見ることができる。
過去100年間、ニューヨークの人口は3つの段階を経てきた。まず、人口が穏やかに増えた第一段階である。人口と経済活動は持続的に集積され、1950年には789万人まで膨張した。次は、人口増が人口減へと転換した第2段階である。「都市病」の激化に伴い、都市機能拡散計画が実施され、人口は周辺都市へ移動した。1980年には707万人まで人口は縮小した。1980年代を起点とする第3段階では、都市計画の見直しと産業の高度化により、人口が回帰し、2015年には855万人にまで増えた。ニューヨーク大都市圏の人口規模から見ると、1950年はすでに1,000万人を超えており、今日はさらに1,859万人に達した。
東京も似たような葛藤を経験した。
第二次世界大戦後、日本は都市化がハイスピードで進んだ。大量の農村人口が大都市、特に東京へ集中した。東京都内の人口は1965年に889万人になった。1960年代、蔓延し続ける「都市病」に対応し、東京の「過密」問題を解消するために多摩ニュータウン、港北ニュータウン、千葉ニュータウン、さらには筑波学園都市などの新都市が、東京周辺地域に次々とつくられ、製造業の地方移転と人口の郊外居住化が同時に進んだ。1995年になって、東京都の人口は797万人まで減った。
1990年代中後期、人口の郊外居住化が終焉を迎え、「都心回帰」が始まった。都市再生計画の実施や都市インフラの整備により、東京都市部の人口は再び増大した。2015年、東京都の人口は1,353万人を超え、東京大都市圏の人口規模は3,800万人に達した。
3
ハワードの予言に戻る。
都市圏の視点からすると、大都市人口と経済活動の中心部への集中・集約が「集中化(Centralization)」であり、周辺地域への分散を「分散化(De centralization)」と称するなら、ハワードの予言は「分散化」志向であった。
しかし、世界の都市の進化の過程で明らかになったのは、集中化と分散化は実際には、都市の進化の表裏であり、時には集中化は分散化を圧倒し、時には集中化はまた分散化に圧倒される。また時には双方伯仲し強弱つけ難い状況になる。しかし、総じて集中化の力がより強い。
事実上、ロンドン、ニューヨーク、東京などのメガシティでは、ほとんど集中化から分散化に進み、再び集中化に戻ってくる過程を辿った。
都市は集積効果によって発展し、集中化の現象が起こる。しかしその人口と経済活動の集積がある「極限」に達すると、「規模の不経済性」が芽を出し、分散化の力量が働く。
その結果、人口と経済活動は周辺地域へ移り始める。
しかしながら、分散化が起こる時、往々にして集中化のパワーはなりを潜める。一定の時期が過ぎて、集中化の力は再び分散化を圧倒し、さらに新しい集積を引き寄せる。
集中化と分散化の増減の背後には「効率」がある。効率を決定づけるのは交通インフラ水準であり、技術水準であり、都市の智力水準である。
交通インフラ水準を整備し、技術水準と都市の智力水準が向上すると、集積に対する都市の積載力を高められる。「大都市病」は、都市の過大さゆえに起こったのではない。その交通インフラ水準、技術水準、都市の智力水準が都市の「大きさ」に耐えられなかったため起こったのである。
50年前に東京都の人口が889万人だった頃、「都市病」が蔓延しているとの焦燥感に悩まされた。しかし今は、東京の人口はすでに1,300万人を超えているにもかかわらず、「過密」だとの訴えは聞かない。
何故なら、現在、東京の交通インフラ水準、技術水準、都市智力水準が以前と比較できない程向上し、都市の積載力も格段に上がったからである。
都市の積載力は固定的なものではない。時間と空間の変化によって異なってくる。同様の時期でも都市ごとに積載力には大きな違いが生じる場合もある。同じ都市でも時期ごとに積載力は異なってくる。総じて、交通インフラ水準、技術水準、都市智力水準に応じて都市の積載力は増していく。
4
国の視点で見ると、大多数の国の都市化が、集中化から分散化、そして集中化に再度戻る過程を辿っている。
人口流動を参考にした世界主要国家の都市化過程は、4つの段階に分けられる。第1段階は、中小都市化段階である。人口が農村から都市へ流れ、都市化の主体は中小都市である。
第2段階は、大都市化段階である。都市化率が50%前後になった後、人口流動の主要形態は中小都市から大都市へと流れる。農村人口は中小都市に流れる場合もあり、また大都市に直接流れ込む場合もある。
第3段階は、大都市の郊外化段階である。都市化率が70%前後に達し、人口が大都市の市街地から郊外へ流れる段階である。
第4段階は、大都市圏とメガロポリス段階である。郊外は中小都市へと進化し、大都市の中心市街地とタイアップして大都市圏を形成する。さらに複数の大都市圏が連携を緊密にすることでメガロポリスが形成される。
第1段階と第2段階が集中化である。第3段階は分散化で、第4段階は再集中化である。
都市発展のこうしたS字型曲線は中国の都市化で検証できる。
改革開放以来、中国の都市化は先進国が100〜200年間かかった道のりを、たった40年間で走り抜けた。
1978年、中国の人口都市化率はたった17.9%に過ぎなかった。しかし2016年には57.4%にまで急上昇した。
1980年代、郷鎮企業の急速発展に伴い、小城鎮が中国各地に出来上がり、中国都市化率は急速に向上した。その意味では1980年代は中小都市の時代である。
1990年代は、大都市の時代である。大量の労働人口が農村や小城鎮から大都市へ流れた。政策上では、1980年代にも「都市病」への憂慮から「大都市の抑制」が高らかに掲げられた。しかし実際には、集積効果が威力を発揮し、大都市化は急速に進み、中国の大都市がことごとく工事現場化した。
西暦2000年、中国の都市化率は36.2%台になった。「大都市の抑制」も政策から外した。
この頃はまた、上海、北京を代表する大都市が中心市街地の「過密」の解消に乗り出し、郊外化を発動した。例えば、上海では嘉定、松江、青浦、南橋、臨港の5つのニューシティが建てられた。これらのニューシティは一定の人口を受け入れたものの、人口密度の高い集積地には至らなかった。
40年の道のりを振り返ると、中国の都市化と世界主要国の都市化の過程は、本質的に似通っている。
ただ、中国の国土が巨大なゆえに地域ごとに発展段階が大きく異なり、例えば西部地域はまだ第2段階にある。そして珠江デルタ、長江デルタ地域はすでに第3段階、第4段階に突入している。
ノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・E・スティグリッツ氏は、中国の都市化はアメリカのハイテクの発展と並び、21世紀の人類社会に影響を与える二大ファクターであると言う。中国改革開放後の40年の都市急速発展は、長江デルタ、珠江デルタ、京津冀などメガロポリスを誕生させ、人口と経済活動を大都市へと集約させた。この過程において、分散化の力学も働いたものの、やはり、集中化の力学が圧倒的であった。
5
中国では、都市化政策において、中小都市を主体とする分散型都市化と、大都市を主とする集中型都市化という二つの主張が従来より戦いを繰り広げてきた。
これからの中国の都市化は集中化で進むのか、分散化で進むのか?
筆者は4つの理由で集中化を進めるべきだと考える。
第一に、都市規模が大きくなればなるほど、産業の集積が大きくなり、就業機会と収入も多くなり、生産コストと交易費用は低くなる。インフラ整備と公共サービスコストの分担も減る。
これと反対に、都市規模が小さくなればなるほど、規模の経済性は実現しにくくなり、インフラの効率も悪くなる。
世界銀行の研究では、人口規模が15万人以下の都市では、規模の経済性は実現し難いという。
これに対して、「中国では多くの中小都市が素晴らしいパフォーマンスを見せている」との意見が出るかもしれない。
実は、中国でパフォーマンスの良い中小都市の殆どは、大都市の周辺に位置している。中国のもっとも末端の都市単位の「鎮」で見ると、経済ランキングトップ100の「鎮」のうちの90%が、ことごとく長江デルタか珠江デルタの中心エリアにある。こうした中小都市の繁栄は、両デルタ地域の巨大都市に依存していることが明らかである。
これは都市化のメカニズムがもたらした現象である。政策はメカニズムに反することをしてはならない。
第二に、都市化の第2段階は、国際経験的に都市化率が50%から70%に向かう段階である。この段階では人口が主に大都市へと向かう。アメリカでは、人口500万人以上の大都市の、全国での人口ウエイトが、1950年に12.2%だったのに対して、2010年にはその倍の24.6%に達した。日本では東京、大阪、名古屋三大都市圏の、全国での人口ウエイトが、1920年に35.8%だったのに対して、2015年にはほぼ1.5倍の53.6%に達した。
2011年から2015年の間で、中国で常住人口増加が最も進んだ都市は、北京、上海、広州、深圳、天津の5都市で、これらは中国で「一線都市」と呼ばれ、この間、年平均1.9%で人口が増えた。また、省政府所在地である省会都市など「二線都市」と呼ばれる都市には、二つのグループがある。一つのグループは9つの都市で、この間、年平均1.2%で人口が増えてきた。もう一つのグループは19都市で、この間年平均0.9%で人口が増加している。ところが、43ある「三線都市」は、この間、年平均人口増加率はたったの0.4%でしかなかった。この間、中国の人口自然増加率が0.5%であることに鑑み、「三線都市」はすでに人口純流出状況にある。
大都市ほど人口に対する吸引力があることは、潮流であり、政策は潮流に逆らってはいけない。
第三に、中国では大都市の「過密」を理由に、中小都市の発展を推し進めるべきとの政策主張がある。
しかし、先進国と比べ、中国の大都市への人口の集約はまだ低く、大都市における人口密度も決して高くはない。上海は中国最大の都市であるが、その人口規模は、全国における比率が僅か3%に満たない。これに対して、イタリアの半分の人口が8%の国土に暮らしている。アメリカの郡の数は3,000カ所にのぼるが、全国人口の半分は、244カ所の郡に片寄っている。東京都の面積は日本の国土面積のたった0.6%に過ぎないが、日本の10%の人口を抱えている。
実際に、中国の都市を悩ませているのは人口の規模ではなく、交通インフラ水準、技術水準、そして都市の智力の水準が、先進国と比べまだ低いことである。
大都市へ人口が集中していくことはすでに世界的な常識であり、政策は常識に反することはしてはいけない。
第四に、そこにやって来た人には、住み続ける磁力を与えることが大都市の腕前であろう。2015年以前は、中国では「北京、上海、広州から逃げる」というフレーズがあった。しかし実際はそれに反して、中国の人口は一貫してこれらの大都市に流れていった。
大都市ではより多くの就業機会、より高い給料、より多彩な刺激、より様々な娯楽があり、レストランでもより多くのメニューが並んでいる。中小都市は、真似ることができない。
人は永遠に利に乗じて害を避けようとする。人々は、どこにチャンスが多いか、どこの収入が高いか、どこの生活がもっと快適で、より刺激的かを求め、流れる。もちろん、一つ大前提がある。それは、人々が自分の住処を自由に選択できるという前提である。
より良い生活を求めて移動する、これこそが人間の本能であり、政策は人間の本能を押さえ込んではいけない。
6
中国共産党第19回大会の報告で中国都市化の新しい進路が提出された。これは「メガロポリスを主体として大中小都市の協調発展を進める」ことである。
「メガロポリスを主体とする」のは、正確かつ現実的な選択であろう。
今日の国際経済競争はすでにメガロポリスを主体とする競争へとシフトしている。一国の経済発展も、すでにメガロポリスの発展に関わっている。アメリカでは大ニューヨーク地帯、大ロサンゼルス地帯、五大湖一帯の三大メガロポリスが、全国GDPの67%を稼ぎ出している。日本では東京、阪神、名古屋で構成する太平洋メガロポリスが全国GDPの64%を担っている。
中国ではすでに省を単位とする行政区経済が、メガロポリス経済へとシフトし始めている。京津冀、長江デルタ、珠江デルタの三大メガロポリスを合わせた中国国土面積の5.2%にあたる地域が、全国GDPの40%を稼いだ。
ところで、メガロポリスは、どこが主体となっているのか?
答えは中心都市である。
実際、都市の輻射力の強弱によって国際都市、全国的な中心都市、地域的に異なった様々なレベルの中心都市が作られている。これら中心都市をコアに、メガロポリスが形成されている。
中心都市には、「集積が集積を呼ぶ」循環が働くゆえに発展する。中心都市の輻射力の強弱もまた集積の規模と強く関係している。
しかし現在、中国では北京、上海のような大都市で外来人口の移住に対して厳しい抑制政策を取っている。憂慮すべきである。
7
大自然には、「大樹の下に草は生えない」という現象がある。大樹の発達した根が、周囲の水分および各種養分をことごとく絡め取るだけではなく、嵩のある樹冠が陽光を遮り、足元に野草すら生えなくする。
中心都市がもし周辺に恩恵を与えず、養分を吸い取るばかりであるなら、それを中心都市と呼ぶことはできない。
中心都市たるものは、輻射力をもってメガロポリス、さらに世界へと恩恵を与える存在であるべきである。
シリコンバレー創業の父、ポール・グラハム氏は、一国の中には総じて1つか2つの都市が若者の視線を集め、そこでは、国の躍動感が得られると語った。
それはまさに日本にとっての東京であり、イギリスにとってのロンドンであり、アメリカにとってのニューヨークであり、フランスにとってのパリである。
中国にとっては北京、上海、広州、深圳がこうした都市である。しかし、それだけではもう足りない。中国は少なくとも10カ所以上のそうした輝かしい中心都市が必要なのであろう。
フラットではない中国をリアルに
(一)
2005年に海外から北京に戻った周牧之教授が、私に『The World is Flat』という本をくれた。
周教授はこの本はアメリカで評判を呼んでおり、「世界は平らになった」という観点が非常に面白いと言う。個人は国家や会社に代わって世界の主人公たりうるようになってきた。能力と想像力さえあれば、世界中のすべての資源にアクセスすることができる。世界は小さくなった。科学技術と通信の領域は電光石火で進歩を遂げ、全世界の人々がかつてないほど相互に接近している。
次いで、話題を呼んだアメリカの映画があった。一人のアメリカ人がインドへ行き、自分の仕事を将来的に奪うだろうインド人を訓練する葛藤を描いた映画の、その背景はグローバリゼーションである。ますます多くのアメリカ企業が業務を海外へ移転し、インドや中国の安価な労働力を利用した。世界はまさに平らになり、アメリカの高度はゆっくりと下り、インドや中国が高速でのし上がった。
この映画の名前も「The World is flat」だ。
(二)
その後10年が過ぎた。
世界の構造は大きく変化した。
なかでも中国の勃興は最も目を見張るものであった。
中国のGDPは2006年の2.75兆ドルから2016年に11.2兆ドルへと増長し、その経済規模も世界第2位へと躍進して久しい。
近年、ニューヨーク、パリ、東京の観光スポットやブランドショップで、最も頻繁に目にするのが中国人観光客の一群である。2015年に中国人の海外旅行客は1.35億人にのぼり世界第1位となった。
(三)
10年前、BRICs4カ国は、投資家を大いに興奮させた。しかし現在、ブラジルとロシアは経済停滞の中で喘ぎ、新興国の栄光も色あせた。
過去10年間で、一つまた一つと「失敗」国家が現れた。これらの国は経済停滞に見舞われただけでなく、社会不穏にも悩まされている。
アメリカのメディアによる「最も失敗した30カ国」リストがある。これを見た後の感想はといえば、「確かにこの30カ国は失敗した。しかしもっと失敗した国がこれ以外にまだある」。
実際、過去10年間で、中国など数少ない国がグローバリゼーションの中で大きな収益を上げることができた。一方で相当数の国が大変な代償を払った。世界は平らになったのではなく、凸凹はむしろさらに進んだ。
(四)
周教授は「過去の10年間、日本では東京大都市圏だけが166.4万人も人口が増えた。これに対して他の数都市は微増で、ほとんどの都市が人口減少状態にある」と紹介した。
「過去の10年で人類の経済活動はさらに大都市に集中した。こうした大都市は世界で最も優秀な人材、経済資源、最有力企業を集められる」と、周教授は強調した。
(五)
周教授は、中国の凸凹も進んだと述べている。
周教授と彼のチームが作り上げた〈中国都市総合発展指標〉はこれをリアルに表現している。
同〈指標〉では、偏差値を用いて都市の各方面のパフォーマンスを表現している。
たとえば「医療輻射力」項目では、偏差値が60以上の都市は、22都市であり、なかでも北京、上海の偏差値は100にも達している。これに対して、偏差値が45以下の都市は27都市もある。これは激しい凸凹である。
「人口流動」項目では、偏差値60以上の都市、つまり外部から人口が大量に流入した都市は16都市ある。なかでも3都市が偏差値100に達している。これに対して偏差値が45以下の都市、すなわち人口が大量に流出した都市は46都市もある。これもまた不均衡である。
同指標を立体的に表現するグラフは数多くある。こうした立体図の中には、目を見張るような山峰があり、一方で深く沈む峡谷もあった。しかも山峰はさらに輝きを増し、峡谷は谷底深く落ち込み続けているのだ。こうした状況は決して軽視できない。
(六)
周教授は、不動産市場は中国都市の凸凹状況をよく映し出していると言う。
10年前、ほとんどの都市の不動産価格は上がり続けた。もちろん価格上昇幅は、一部の都市は大きく、一部の都市は小さかった。しかし現在、一部の都市の不動産価格が上がり続けるのに対して、一部の都市は停滞もしくは下落している。
不動産価格の上昇と下落は、都市の浮き沈みを表している。その背景には、さまざまなパフォーマンスの違いがある。都市競争時代にあって、ある都市は邁進し、ある都市は停滞し、ある都市は転落している。
(七)
『The World is Flat』で、著者フリードマンは幼い頃に両親が常々彼に言っていた言葉を振り返っている。「トーマス、ご飯は残さず食べなさい。忘れないでね、中国人はいま飢えに喘いでいるのよ」。
〈中国都市総合発展指標〉は、この言葉と同様なことを語っている。
現在はフラットの時代ではなく、凸凹時代である。
(八)
凸凹道には、道標が必要である。
周牧之教授の〈中国都市総合発展指標〉は、斬新な道標を指し示してくれている。