
■ 編集ノート:
小島明氏は、日本経済新聞社の経済部記者、ニューヨーク特派員・支局長、経済部編集委員兼論説委員、編集局次長兼国際第一部長、論説副主幹、取締役・論説主幹、常務取締役、専務取締役、日本経済研究センター会長、政策研究大学院大学理事を歴任、日本記者クラブ賞、ボーン・上田記念国際記者賞を受賞。新聞協会賞を共同受賞。
東京経済大学の周牧之教授の教室では、リアルな学びの一環として第一線の経営者やジャーナリスト、官僚らをゲスト講師に招き、グローバル経済社会の最新動向を議論している。2023年12月7日、小島明氏を迎え、講義をして頂いた。
■ 「日本の失われた30年」の三つの原因
周牧之:最近話題になっているのは、「日本の失われた30年」が中国で繰り返されるのかどうかだ。私から見ると「日本の失われた30年」には原因が三つある。一つは消費税だ。消費税ではなく交易税という名にすべきだった。買い物をするときだけに払う税金だと思いがちだが、すべての交易にかかる税金だ。
アダム・スミスの『国富論』第1章は分業論だ。グローバリゼーションが1980年代から進み、各国の関税は軒並み低くなった。国内で取引するたびに消費税を取られることが、国内における分業を妨げ、海外との分業を後押しした。日本はその交易税的な本質を見極めず1989年に消費税を導入した。その後バブルが崩壊し日本経済は長い停滞期に入った。
二つ目はデリスキングの経営思考だ。大手企業、財界を見て強く感じるのは、経営リスクを取らないサラリーマン社長が多いことだ。リスク負いを避けたい人が多い。1989年平成元年の世界時価総額トップ10企業には日系企業が7社もあった。しかし時代が急変し、現在同トップ10社に日系企業の姿は無くなった。代わりにイノベイティブなスタートアップ企業が8社入っている。全て創業20〜40年のテック企業だ。これに対して、日本ではイノベイティブなスタートアップ企業が少ない。現在、日本の時価総額トップ30企業の平均創業期は1919年で、平均年齢は100歳を超えている。
小島明:その通りだ。

周:三つ目は小選挙区制の導入だ。小島先生が信奉するドラッカーの発想の根底には、「すでに起こった未来」を確認することがある。ドラッカーは人口動態問題も知識社会の到来も世間に伝えた。その意味では日本にとって大切なのは現状をいち早く確認し、対処に取り取り掛かることだ。ドラッカーに関する小島先生のご著書には「日本は組織のイノベーション、社会のイノベーションがあまり問われない」とある。大変革時代に日本で組織的社会的なイノベーションが問われない理由は、小選挙区制の導入により政治力、政治家の質が劣化したからだ。時代変革の確認ができず、社会、組織のイノベーションが進まない。
小島:周先生が言う「日本の失われた30年」の原因の、二つ目と三つ目は100%同意だ。一つ目は半分賛成。アメリカやヨーロッパには消費税という名でないセールスタックス或いは付加価値税と言われる税がある。各取引段階で、ダブらないよう調整する税だ。税率は、日本では10%。ヨーロッパだと25%。消費者個人の租税負担率では日本の方が低い。分業がうまくいかない最大の問題はリスクテイクができないことだ。
周:ここ数年多くの企業家から話を聞いた。「商売していて10%利益を上げることは大変なのに、取引するたびに税金が10%とられ、たまったものではない」と言う。欧米諸国も生産過程で取引するときに消費税が発生するなら、必ず国の産業空洞化につながる。
消費税にしても小選挙区にしても、導入過程での議論の際に比較対象を間違い易い。日本は1億3,000万の人口がある。ヨーロッパ、特に北欧には小さい国が多い。日本は、自国の10分の1も無い人口規模の国の政治制度や税制度を国の制度改革モデルとする際、人口規模の桁違いを意識すべきだった。
昔中国も同様なことが起こった。秦の始皇帝が中国を統一したものの十数年で崩壊した。諸説あるが、始皇帝が秦の制度を中国全土に一気に拡大させ、機能不全が起こったのが原因だ。桁の違う国土と人口の制度設計を簡単に一緒にして議論するのは危険だ。
小島:税金を払っても生きていける体力があるかどうか。
周:税には良税と悪税の二種類ある。私は資産税を悪税ではないと考える。しかし取引税は分業を妨げる悪税だ。特に今の時代、関税が限りなく低くなっており、国内での取引税は海外との分業を推し進め、空洞化を産む。グローバリゼーションの観点からすれば悪い話では無いかもしれない。
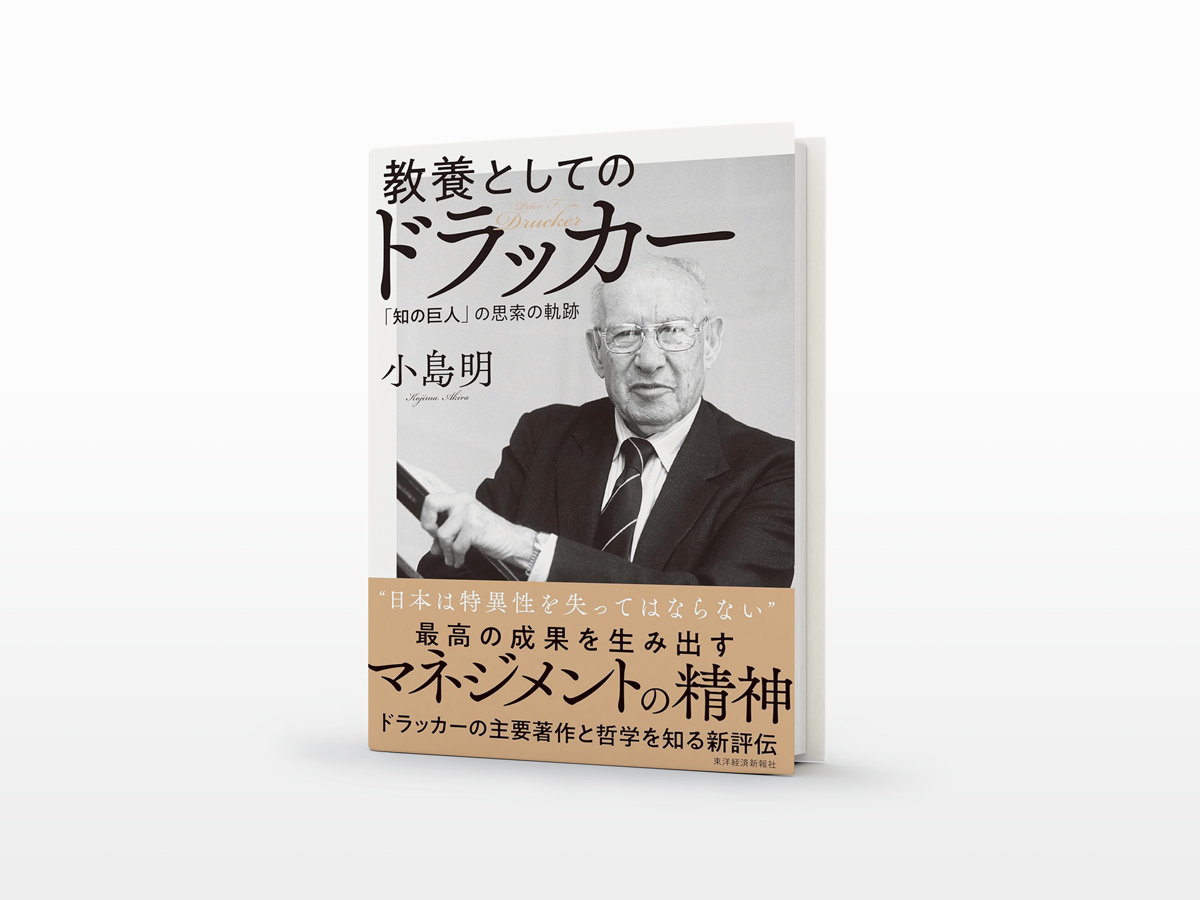
■ ゾンビ企業の生き残り作戦
小島:リスクの問題について言えば、日本にはバブル崩壊後に収益を上げた企業があった。しかしその多くは新しい事業を始めたのではなく、人件費をカットした企業だ。人件費カットの仕方はボーナスを出さず、ベースアップをなくし、正規社員の2分の1か3分の1の賃金で働く非正規の人員を増やす、など様々ある。バブル崩壊前、全労働人口のせいぜい15%が非正規だった。今は非正規が4割近くにのぼり、企業側は人件費が節約できる。借金を返し、海外に行かず、投資はしないからビジネス機会が生まれない、雇用も増えない、賃金も上がらない。
周:つまりリスクをとって積極的な投資とイノベーションで利益を出すパターンではない。
小島:リスクテイクをする資本家や企業経営者がいなくなった。バブルが崩壊し、金融機関までおかしくなったのは日本にとっては初めての経験だ。
とくにデフレが始まった1998年の前年末に三洋証券が破綻し、北海道拓殖銀行などの銀行が潰れた。銀行が貸しはがしをし、投資を一生懸命やろうとした企業に、「お前のところは儲かっているから貸した金を返せ」と迫った。経営がダメな赤字の会社は返す金がない。そこを貸し倒れにすると帳簿上、金融機関の損になる。その損を出したくないから転がして追い貸しをする。儲かっている企業から現金を回収し、経営が駄目なところに転がしてやる。日本企業の99%が中小企業と分類されている。政治も中小企業は弱者だからと助け、銀行は追い貸しでいいから貸せと言った。結果、やる気がなく儲からず普通は持続できない企業が長生きしている。
これはゾンビ企業だ。新陳代謝ができない。この分野は不必要、或いは続けたいが黒字の見通しなく赤字だという企業を援助すれば、経営者から政治家に給付金や献金が来る。日本のバブル崩壊後の対応として本来ゾンビ企業は市場から撤退させ、新しい人材や資本で新たな可能性を広げる必要があった。ところが、ゾンビ企業にカネが使われてしまった。国の財政もゾンビになった。バブルがはじけ不況が長引き事業転換しないと経営が苦しくなる。人件費節約を経営テーマにし、人事部や総務部など国内派が主導した。投資についても支出で収益が減るから投資しない。銀行からの借金は全部返す。株主がうるさいから自社株買いで買い戻す。全体のマーケットにおける株の供給が減るから値段が上がり株主だけでなく役員、従業員も株でもらえる。
周:その結果、日本企業には、積極的な投資とイノベーションで新たな製品やサービス、マーケットを創出する勢いがなくなった。

■ チャレンジしない組織体質
小島:日本の場合はボトムアップではない。社長が人事権を持ち、人事が気になる社員が社長の顔色をうかがいながら仕事をする。社員みんなの意見聞いて社長がそれに従うのではなく、人事権を通じた徹底的なトップダウンだ。日本では、上場も非上場企業もバブルがはじけた後に怪我せずリスクを取らず、生き残った人が企業のトップになった。人事部、管理部など内部をやった人たちだ。海外でビジネスをし、マーケットを開いた人は、なかなかトップになれない。
周:第一線で頑張っている人たちが評価されず、トップにも入り難い。これが企業の経営に大きな影響を及ぼしている。
小島:経理屋、人事屋は、新しいアイディアが下から来ると、マイナスだ、危険があると列挙し、やってみなければわからないのに可能性を考えずネガティブなことだけ列挙した。
日本からベンチャーは出難い。ベンチャーキャピタルは銀行が作った子会社だ。銀行は絶対リスク取らず、貸したら必ず担保を取り、企業は潰れても担保の不動産はもらう。つまりリスクを取らないビジネスをやっている。いわゆる投資銀行は日本にないため、大蔵省の制度がそうしたやり方で、技術が海外にあれば技術をもらい、確実にこの技術を使えるとなるとカネがつく。ノーリスクでできると考えたからだ。
技術のリスクは、例えば海外で鉄鋼生産、造船、自動車などそれぞれの国が既にリスクをクリアした産業を、日本が導入した。だから先行した国の後で動かせばいいだけだった。リスクテイクはしなかった。リスクの語源は古いイタリア語から来ていて、可能性にチャレンジする意味だ。可能性、将来性だ。今、日本はリスクというとネガティブにとらえ背を向けて逃げる。オーナー企業の経営者には一部まだリスクテイカーがいるが…
周:森ビルの森稔社長は、中国でリスクを取って大きなビルを上海で建てた。大勢の人にやめた方がいいと言われても、やり遂げた。結果、大成功した。
小島:そうだ。人事部が取り仕切る企業は社長がこうしたリスクを取らない。日本は第二次世界大戦後に一時勲章制度を無くしたが、復活させた。勲章をもらうには産業、経済団体のトップにならないと難しい。このため団体トップの順番を待つから、日本は老人支配の社会になる。今の経済人は年を重ね経営能力を失っても会長、名誉会長、特別顧問として会社に居続ける。亡くなるまで社内に自分の部屋があり、秘書に支えられゴルフをする。次の人はその人たちから選ばれるから、誰も辞めさせられない。人事で動く世界だから、ボスの顔をいつも見ている。社長の仲間ばかりが上に行く。海外に出張し海外事業で成功しても数字上でしかトップはわからない。
日本はリスクを取らない。リスクは潜在的な可能性を持ち、もとより危険なものだ。リスクマネジメントが重要だ。リスク評価とリスク管理の発想は、バブル崩壊後、日本から消えた。

■ 個人が最大の価値を発揮できる組織を
周:根底に必要なのは正しい組織論だ。ドラッカーの組織論は、マネージメントを定義した。組織の個人が最大の価値を発揮でき、価値を作り出すことができるのがいい組織だ、とした。
小島:人材はコストでなく、資産であるという発想だ。経営者がみな読んだ1973年出版の“経営のバイブル”とされた『マネジメント』の中で、ドラッカーが繰り返し強調しているのはこのことだ。日本はバブル崩壊後、人材がコストとみなされた。人は少ない方がいいし、賃金は安い方がいい。
周:誰にでも取り替えができる人がいい人材で、人が辞めても同じ働きのできる人がいれば良しとする考え方が日本には根強い。昔の工業時代の人材の価値の見方だ。ドラッカーが言う知識社会の発想ではない。知識社会は個性が大事だ。
小島:その通りだ。
周:本来、組織の中で権力はいらない。権限とは権力ではなく責任だ。それが今の日本の組織の中では、逆になっている。
小島:本当にそうだ。いつの間にか逆になった。
バブルがはじけた後の不良債権処理が長引き、銀行が駄目になった。プラザ合意の1985年、日本の投資率が高かったとき、企業は自前の資金が足りず銀行からどんどん借りた。ところがその後日本の企業は成長見通しを下げ、投資率は下がった。貯蓄率はそのままで貯蓄余剰経済になってしまった。金融機関は従来、頭を下げて金を預かったが、余るようになった。結果、リスクを取らない銀行は、土地さえ担保であればいくらでも貸し、それがバブルを生み出した。地価が暴落した。
1985年から金融機関が資金余剰となり体質改善の必要が出た。ところが金融機関は未だに同じ体質のままだ。ベンチャーやリスクテイカーを応援することにはなっていない。例えばマイクロソフトのビル・ゲイツが日本で創業したいとなったら、日本では彼に金を貸す人は出てこなかっただろう。ゲイツが、私はアイディアを持っていると言っても有形の担保が無く自分のオフィスも無い。賃貸ビルで、自前の工場は持たず、委託生産だ。持っているのは無形のノウハウだけである。日本の従来の金融機関ではそれは担保と見做さないから、断っただろう。日本では起業家を応援する金融システムがない。社会のニーズに対応する金融システムのイノベーションが必要だ。
イノベーションは単に、ものを新しく作るだけではなく、時代のニーズに対応できるシステムイノベーションが欠かせない。

■ 元気な新しい企業が出てこない
周:平成元年の1989年、世界時価総額トップ10企業の中に日本の銀行は5社入っていた。その後これらの銀行は合併を繰り返し、いまや世界時価総額トップ100企業の中に1社も入っていない。
小島:100社内にいる日本企業はトヨタともう一社くらいだ。
周:ゾンビ企業は大問題だが、ゾンビ以上に問題なのは元気な新生企業が少ないことだ。いま日本の時価総額トップ30企業のうち1980年代以降に創立した企業はたった一社、ソフトバンクだ。
小島:企業の少子化、設備の高齢化、資本ストックの高齢化が、日本の資本主義の問題だ。

■ 小選挙区制の弊害
小島:小選挙区問題もするどい指摘だ。政治劣化の原因は、小選挙区と政党助成金だ。官邸が役人の幹部に対する人事権を持った。このため役人が何も言えなくなった。
周:マスコミも批判しなくなった。日本は選挙で選ばれた人々が政治家に、勉強で選ばれた人たちが官僚になる。公務員試験に受かった人たちが責任ある立場に立ち、実績を作りながら上に行く。さらに企業家、学者、マスコミが加わって、互いにチェックし依存し合うシステムだった。ところが、小選挙区の導入で、政治一強、官邸一強となり、官僚もマスコミも小さくなった。
財界も迎合する。経団連が消費税を推進している。不勉強なのか、立場を忘れているのか、財界が消費税という取引税を推進すること自体が不可解だ。
小島:小選挙区導入当時は、政治改革すればいいという空気の中で、反対すると守旧派と言われ、言論封殺される。小選挙区の結果、二世議員、三世議員が増えた。しかも、政党助成金の名目で税金から政治資金が各政党のトップに行く。自民党であれば首相と幹事長から「次は公認にしない」と言われれば、選挙に出られずカネも来ない。自民党の中にも、昔は宏池会などさまざま派閥があり、政策論争もやった。今は政策論争がなくなった。
周: その意味では昔の方がずっとバランス良く面白かった。
小島:今の政治家は、個人的に話している時は「問題はある」と言うが、リスクは取りたくない。日本の政治は、今だけ、自分だけ、口先だけの「三だけ政治」だ。アメリカも反知性主義的選挙になっている。
東京大学の学長だった佐々木健は「日本の民主主義は、選挙ファンダメンタリズムだ」と言う。選挙さえ通れば良く、選挙が頻繁にあって短命の政権になる。平成の30年間で日本は17人も首相が生まれた。平均寿命が2年もない。選挙でお礼回りし、少ししたら次の選挙の準備が始まる。宇野宗佑や羽田孜のように2カ月ぐらい或いは数十日しかもたない首相もいた。皆が順繰りにポストが回ってくるのを待つ。安倍政権も長期政権とは言えず、6回国政選挙があった。次の選挙が近ければ、選挙前のあらゆる政策は、次の選挙のプラスになることしかやらなくなる。3年我慢し、4、5年経ったら花が咲き、実がなるという政策が、いま全部お蔵入りし、選挙目当てのバラマキ政治になった。
周:明らかに制度設計のミスマッチだ。民主主義は主義だけでなく制度設計の知恵、知識が必要だ。間違った設計がされたら大変なことになる。ドラッカーが言う社会的イノベーションが必要だ。また、安倍長期政権の一つの理由は、その前の民主党政権が酷すぎたからだ。

■ 百花斉放の自由政策が繁栄をもたらす
小島:失われた30年の原因について、もう一つ私が付け加えたいのは、行政のレギュレーション、規制の問題だ。司馬遷の史記の列伝集『貨殖列伝』に、良い政治は民がしたいようにさせ、次善の政治は民をあれこれ指導する、一番悪い政治は民と利益を争う、とある。古代の中国では自由なときには百花斉放があり、自由な議論があり、文化も経済も発展した。
周:歴史上、中国の繁栄期は全て百花斉放の時だ。漢の文帝・景帝の時代、道学をベースとした自由政策をとり、百花斉放を謳った。その結果、「文景の治」という大繁栄期を築いた。しかし武帝になると、規律規制を重視する儒学を国学とし、それ以外の諸学が排除された。政府が前面に出て対外戦争も次々仕掛けた。結果、漢王朝は一気に下り坂になった。司馬遷は漢武帝の政策に批判的だった。その反省も込めて良い政治、偽善の政治、一番悪い政治というジャッジメントをした。
延安時代の毛沢東は百花斉放を提唱し、共産党の勢いを形作った。
小島:ところが日本は規制大国だ。総務省が調べたものに、法律、政令、省令、通達、規制、内規、行政指導がある。役所の書類には、少なくとも20種類の言葉がある。評価、認可、免許、承認、承諾、認定、確認、証明、臨床、試験、検査、検定、登録、審査、届け出、提出、報告、交付、申告。これを全部明確に定義できる役人は1人もいない。日本における行政の裁量性が今一番の問題になっている。
日本がアメリカとの摩擦を起こしたものの一つに、弁護士事務所を認め法曹界を自由にしろという要請があった。ところが自由にしても、アメリカの法律会社は日本に入ってこない。見えない規制があるからだ。法文を見て弁護士がこれは可能だと考えても、「何々等」という言葉が付いた曖昧な法案だ。法律を解釈して理解できるのは半分だけで、残りは役人が裁量権を持つ。接待がバブルのときに頻発したのは役人による裁量行政があったからだ。役人の裁量、権限は、不透明かつ裁量性だ。どの範囲でどう解釈されるかで、企業の存亡が決まることが沢山ある。デジタルも共通の言語がない為、役所ごとに解釈が違う。例えば、デジタルの世界ではモノ作りは経産省、通信は総務省で、繋がっていなかった。
日本は長らくIT(情報技術)論であり、ICT(情報通信技術)の発想でなく、C(通信)が抜けた発想の政策だった。
周:政治家や官僚だけでなく、日本の経営者も学者も規制を作るのは大好きになった。大学の教授会ですら規制作りの話が多い。結果、皆リスクが取れなくなった。

■ 優れた経営者はなぜ輩出されなくなった?
周:一昔前には森ビルの森稔、リクルートの江副浩正など日本には優れた起業家がいた。なぜいまいなくなったのか?森稔さんから江副氏とは同級生だと伺っていた。
小島:その人たちは特別だ。実はあまりそういう人はいない。立派なスタートアップ企業がこの30年なかった。唯一ソフトバンクがあるが、これは一種のコリアンブランドだ。小倉昌男が起こしたクロネコヤマトはイノベーション企業だ。彼は、あのモデルが成功したときに沢山の出版社から本書いてくれと言われたが書かなかった。自分がビジネスをやっている間は一切本を書かないと断った。その理由は、ビジネスリーダー、経営者は、あらゆる環境変化にそれぞれの判断でやる必要があり過去に縛られてはいけない、過去の成功体験や前例に捉われず、その都度、真剣な勝負をすることだと言った。
周:昨年50周年を迎えたぴあという会社も学生が作った企業だ。
小島:ぴあの創業者矢内廣が50年間ずっと社長をやっている。
周:立派なスタートアップが昔はあったにも関わらず、この30年はほとんど出ていない。
小島:問題は、技術のパラダイムが変わっているときに、過去の技術でやり続けていることだ。成功体験が今日本の制約になっている。組織内の新陳代謝、発想の新陳代謝が起こらない。行政も縦割りで前例主義になっている。
周:技術のパラダイムシフトに対して、社会のイノベーションが必要だ。
(※後半に続く)

プロフィール
小島明(こじま あきら)/日本経済研究センター元会長
日本経済新聞社の経済部記者、ニューヨーク特派員・支局長、経済部編集委員兼論説委員、編集局次長兼国際第一部長、論説副主幹、取締役・論説主幹、常務取締役、専務取締役を経て、2004年に日本経済研究センター会長。
慶應義塾大学(大学院商学研究科)教授、政策研究大学院大学理事・客員教授などを歴任。日本記者クラブ賞、ボーン・上田記念国際記者賞を受賞。新聞協会賞を共同受賞。
現在、(一財)国際経済連携推進センター会長、(公財)本田財団理事・国際委員長、日本経済新聞社客員、(公財)イオンワンパーセントクラブ理事、(一財)地球産業文化研究所評議員
主な著書に『横顔の米国経済 建国の父たちの誤算』日本経済新聞社、『調整の時代 日米経済の新しい構造と変化』集英社、『グローバリゼーション 世界経済の統合と協調』中公新書、『日本の選択〈適者〉のモデルへ』NTT出版、『「日本経済」はどこへ行くのか 1 (危機の二〇年)』平凡社、『「日本経済」はどこへ行くのか 2 (再生へのシナリオ)』平凡社、『教養としてのドラッカー 「知の巨人」の思索の軌跡』東洋経済新報社。
