■ 編集ノート:東京経済大学の周牧之教授の教室では2025年10月9日、長年の親友であり元環境事務次官の中井徳太郎氏を迎え、日本海そしてシナ海を一つの生命体として捉える発想から、カーボンニュートラルやネイチャーポジティブ、日本的な自然観と祭りの知恵までをつなぎ、「三千年の未来」を見据えた文明論的ビジョンを伺った。ローカルな足元からグローバルなダイナミズムへと視野を広げるこの構想は、現代の生き方と将来像を問い直す大きなヒントになる。
(※前回記事【対談】中井徳太郎 VS 周牧之(Ⅰ)はこちらから)

■ 地球沸騰の気候危機に直視を
中井徳太郎:今、地球環境は「地球沸騰」とも言われる状況にある。今日も台風が接近していて、幸い本土上陸はしないが、八丈島や伊豆大島などで風速70メートルというとんでもない状況になっている。
その背景にあるのは、海面水温の異常な上昇だ。二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスは、太陽光が地表で反射した赤外線を吸収し、大気の温度を、人間や生物が生きられる範囲に保つという重要な役割を果たしている。しかし、産業革命以降、人類が化石燃料という地下資源を大量に燃やし続けた結果、CO₂濃度が上昇し、太陽からの熱を吸収する「保温の膜」の厚みが増してしまった。その結果、大気の温度が上がってしまった。
産業革命以降、平均で見ると地球の気温は約1.1度上昇していると言われている。年によっては1.5度近くになる。ここで言う「気温」は主に大気の温度だが、実際、地球には海という巨大な水の塊があり、大気が温まると、その熱は海にも移っていく。熱容量の大きい海水まで温まってしまったのが、現在の深刻な状況だ。
水を沸騰させると、なかなか冷めない。大気であれば比較的すぐ温度は変化するが、海はそうはいかない。熱容量の大きい海水の温度が上がってしまうと、簡単には冷めない。その結果、水蒸気の量も増え、台風や集中豪雨といった「症状」が出やすくなっている。
異常気象が続いているのに、トランプ大統領のように気候変動そのものに対して懐疑的な立場がいまだに存在する。アメリカでは以前から、「人間の活動が本当に気候変動を引き起こしているのか」という議論が続いてきたが、トランプ大統領は特に「温暖化対策は意味がない」と強く主張している。
しかし、国連を中心に、気候変動についてはすでに膨大な議論と研究が積み重ねられている。気候変動枠組条約に基づき、世界中の科学者の知見を集約したIPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、これまで6次にわたり報告書を出している。その内容は、「人間の化石燃料使用によって大気が温まり、現在の気候変動を引き起こしている」という事実を、科学的にほぼ100%の確度で証明している。
つまり、これは科学的なファクトであり、トランプ大統領が何を言おうと、その科学的結論が揺らぐわけではない。その確立された事実の中で、現在の異常気象は進行している。
周牧之: 気候問題に関するアメリカの政策がバイデンからトランプへの政権交代により大きくブレる中、2024年11月30日開催の東京経済大学国際シンポジウム「グリーントランスフォーメーションにかける産業の未来」で中井さん始め日中の産学官のオピニオンリーダーが両国のGXに関する取り組みを紹介し、議論し合った。アメリカの政策はどうあれ、日中は共にGXを推進していくとの意思を確認し合った。

■ 地球の体質改善にも気候転換点を超えてはならない
中井:地球を人間の身体に例えると、今起きている現象は「慢性病」に近いと言える。メタボリック症候群や、お酒を飲み続けて肝臓が悲鳴を上げている状態だ。ちょっと転んで膝を擦りむいた、という一過性の怪我ではなく、体質改善のために時間をかけて進めないといけない段階に来ている。しかも、すでに症状が出ているので、それが簡単には消えない。だからこそ、今から対処しないと取り返しのつかない「ティッピングポイント(気候転換点)」を超えてしまう危険がある。
ティッピングポイントとは、例えばシベリアなどの永久凍土が本格的に溶け出し、大量のメタンガスが放出されるような状況だ。そこには、古い菌やウイルスが眠っている可能性も指摘されている。こうした「症状」を放置すれば、まさに肝硬変やがんのように、治療が難しい段階に入ってしまうかもしれない。
熱中症や異常気象として私たちの目の前に現れているのは、その「症状」の一部だ。海水温が上がり、大きな渦を巻く台風のような現象が起きやすくなっている。もちろん、台風そのものは自然の循環に必要な面もある。
先週、屋久島に行ってきたが、今年は屋久島周辺で全然魚が獲れないと聞いた。理由の一つは、台風のルートが変わり、屋久島や九州に大きな台風があまり来ていないことにある。台風が来ると、海をかき混ぜる効果があり、表層と深層の水が入れ替わって海の中の代謝が進む。台風が少ないと、温かい表層水がそのまま滞留し、魚にとって適温ではない状態が続いてしまう。自然は非常に微妙なバランスの上に成り立っていることが、こうした現象からも分かる。

■ SDGs、パリ協定そしてカーボンニュートラル
中井:このような状況を受け、2015年には二つの大きな出来事があった。一つは、国連でSDGs(持続可能な開発目標)が採択されたこと。もう一つは、気候変動に対応するためのパリ協定が採択されたことだ。パリ協定では、温暖化の進行を産業革命以降の上昇幅で2度以内に抑えること、できれば1.5度以内に抑えるべきだという目標が掲げられた。
その3年後の2018年には、IPCCが、2度上昇と1.5度上昇では影響が全く違う、0.5度の違いが人類にとって非常に大きな意味を持つとする報告書を出した。海面上昇による島嶼国の水没リスクや、極端気象の頻度などを考えると、できる限り1.5度に抑えたい。そのためには、2050年までにCO₂排出を実質ゼロ(ネットゼロ)にする必要がある、というのが現在の国際的なコンセンサスだ。
つまり、残された時間はあと約25年。2050年までに人類全体としてカーボンニュートラルを達成できれば、科学的なシナリオ分析上、1.5度で温暖化を止められる可能性がかなりある。だからこそ、世界中で2050年カーボンニュートラルに向けた努力が行われている。
一方で、エネルギー需要は増え続けている。スマートフォンだけでなく、AIやブロックチェーンなど、膨大な電力を消費するテクノロジーが次々と社会に組み込まれている。便利さと効率性をもたらす一方で、その裏側で巨大な電力が必要となっている。今の電力供給の多くは、依然として石炭火力やガス火力に依存している。この構造を変えない限り、CO₂排出は減らない。
日本は2020年、菅総理の時代に、2050年カーボンニュートラルを国としてコミットした。当時、私は環境省の事務次官で、小泉進次郎環境大臣とともに、この目標の実現に向けた議論の最前線にいた。日本は非常に真面目な国なので、一度掲げた目標は守ろうとする。2050年ゼロに向けて、2030年には46%削減という中期目標を掲げ、つい最近は2035年に60%、2040年に73%という新たな目標も設定した。
周:中井さんが環境事務次官として、このカーボンニュートラル宣言を支えたことは、大きな政策貢献だ。
中井:現時点では、日本はおおむねオン・トラックで排出を減らしているが、2030年以降が本当に大変だ。技術革新が鍵となる。私は現在、日本製鉄の顧問も務めているが、鉄をつくるには膨大なエネルギーが必要だ。鉄鉱石を石炭で還元する高炉プロセスは、CO₂排出の象徴のような存在で、日本製鉄は日本で最もCO₂を排出している企業の一つだ。その日本製鉄が「2050年に排出ゼロを目指す」と宣言したことは、日本の産業界にとって非常に大きなインパクトがあった。
それまで経済界は、「2050年カーボンニュートラル」に対して慎重だった。できないことを軽々しく口にするのは日本的ではない、できる範囲で現実的な目標を掲げるべきだ、という空気があった。しかし、日本製鉄が「鉄の未来を考えたら、CO₂を出さない鉄づくりに挑戦するしかない」と覚悟を決めたことで、経団連も含め、日本の産業界全体がカーボンニュートラルを真正面から受け止めるようになった。
もちろん、石炭を使わない製鉄や、大量の電力を必要とする電気炉への転換、水素の活用などには、膨大な技術開発と投資が必要だ。政府も税金をベースとした支援を行う必要がある。私はそのあたりも含めてお手伝いをしている。

■ 日本海学と環境政策をつなげた地域循環共生圏
中井:こうして見ていくと、地球環境、特に日本海学でいう「地図を見た瞬間に、ここが一つの生き物のように見える」という感覚──と、現在の環境政策は深くつながっていることが分かる。国境や県境にとらわれず、日本海側には森があり、豊かな海があり、水の循環があり、その中に生きとし生けるものが存在している。この「循環」「共生」「日本海」の視点が、日本海学の三つの視点として整理された。
カーボンニュートラルやサステナビリティを考えるときも、結局は「循環」と「共生」に行き着く。そういう意味では、私にとって日本海学で考えたことを、日本全体の環境政策として展開している、という感覚がある。
周:「生き物」そして「循環」と「共生」の3点セットは大事な視点だ。
中井:私が関わった環境省の政策では「地域循環共生圏」という概念を、閣議決定まで持っていくことが出来た。「地域循環共生圏」は目指すべき社会像として位置づけている。カーボンニュートラル(エネルギーの転換)、サーキュラーエコノミー(循環経済)、ネイチャーポジティブ(自然再興)。この三つを組み合わせた社会を目指そう、との構図だ。
カーボンニュートラルは、「地球に負荷をかけない」というメルクマールであり、2050年までにCO₂排出実質ゼロを目指す。エネルギーを使いながらも、地球全体の健康を損なわない形に変えていく。エネルギーは人間の活動に不可欠だが、その使い方を変えないと、地球という「身体」が持たない。CO₂を増やさないエネルギーの調達・利用構造への転換が求められている。
サーキュラーエコノミーは、経済・社会の仕組みを「すべてがつながっている」という前提で見直し、それを無駄なく循環させる考え方だ。これまで、あたかも地球に無限の資源があるかのように、中東から石油を、大陸から天然ガスを大量に輸入し、それを使って大量生産・大量消費・大量廃棄を行ってきた。プラスチック製品などが典型で、安く大量に作れるがゆえに、簡単に使い捨てられ、その結果、2050年には海の中のプラスチックの量が魚の量を上回る、とまで言われている。地球上のすべてはつながっており、どこかで捨てたものは、最終的に海に流れ着く。だからこそ、「使い捨て」ではなく、「循環」を前提とした経済社会の仕組みをつくる必要がある。
ネイチャーポジティブは、自然との共生を重視する考え方だ。生き物や水、森、山、海など、自然界のあらゆる要素と、どのように折り合いをつけて生きていくか。その関係性を改善し、自然の回復力を高めていく発想だ。
周:地域を生命体として捉える大事な発想だ。
中井:それぞれの地域や主体がそれぞれの持ち場で個性を豊かに発揮し、多様性の中から価値を生み出し、全体を調和させていく。「人間は自然を壊してしまった」との認識が世界共通になる一方で、「ならば人間は自然を回復させることもできるはずだ」という前向きな認識も共有されつつある。これが、ネイチャーポジティブのコンセプトだ。
このとき必要なのは、人間と自然を別々の対象として切り分けるのではなく、「全体が一つの生命体である」という見方だ。
私たちの身体を例にとると、細胞が基本単位であり、父と母から受け継いだ受精卵1個の細胞が分裂を繰り返し、約37兆個の細胞になる。その細胞が心臓、脳、筋肉になり、毛細血管を通じて酸素や栄養が行き渡り、老廃物が排出される。個々の細胞が元気で、互いに連携しているからこそ、全体として身体は調和して動ける。
私は、地球環境や社会も同じように捉えるべきだと思う。一つひとつの生き物、一つひとつの地域・コミュニティ、一つひとつの文化が元気で自立的でありながら、全体とつながっている状態。それぞれ個性を発揮しながら、全体として調和する状態が「共生」だ。

■ 環境・生命文明社会を目指す
中井:生物学や医学の知見も、今まさにそうした見方に近づいている。こうした発想でものを見ることが、新しい時代のキーワード「環境・生命文明社会」だ。
エネルギーも食も水も空気も、できるだけ身の回りで賄い、人間の技術と叡智を使って豊かに暮らす。過度な人口集中によって、都市では大量消費と大量廃棄が進み、いわば自然の「内臓」にあたる農山漁村では人が減り、お金も回らず、田畑や森は荒れている。
このアンバランスを、自立した地域同士の助け合いで是正する。環境省の「地域循環共生圏」は、これを政策として徹底的に進めようとしたものだ。カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを同時に実現していく。
そして、この軸にある発想の原点が、日本海学だ。日本海学で地図を見たときに「ここは全体が一つの生き物だ」とする感覚と直結している。
環境省は、この「地域から循環と共生の世界をつくる」考え方を、「森・里・川・海」という図で表現している。山があり、森があり、里(集落・田畑)があり、川が流れ、海に注ぐ。この中で水が循環し、その循環の中にすべての生き物が存在している。
循環型のシステムは、時間のスケールを伸ばせば、チベットやヒマラヤからガンジス、黄河、長江が流れ出るような巨大な流域の循環にも見えるし、富山なら「山から黒部川を通り富山湾へ」というローカルな循環にも見える。その“流域”というイメージの中に、あらゆる存在が含まれる。だからこそ、「流域」という単位で地域循環共生圏を考えようとしている。
日本海という一つの円環を通して、「周辺の循環」「地域の循環」「アジア全体の循環」と、階層的に循環を見ていく。小さな循環と大きな循環をどう結びつけるか。その接点を議論することが重要だ。
周:そもそも人類の文明は、「流域」単位で誕生してきた。大小「流域」単位で「地域循環共生圏」を構築していくことが、新しい文明のあり方だ。

■ 人口集中と農山漁村の衰退──バランスの崩れ
中井:もっとも現状では、都市部に人口が集中し、農山漁村から人がいなくなっている。田畑は荒れ、森林は手入れが行き届かず、祭りやコミュニティも維持が難しくなっている。一方で、都市部の人々は、食料やエネルギーを外部から大量に買って生活している。その背後に化石燃料などの大量消費があり、地球という「内臓」に負荷をかけている。
このバランスを取り戻すために、AIやITといった最先端の技術も活用しながら、「全体が一つの生命体として調和して循環する世界」「個性が輝きながら共生する世界」をつくっていこう、というのが地域循環共生圏の発想だ。環境省では、これを「環境・生命文明社会」と呼んでいる。単なる経済文明ではなく、「生命」を軸にした文明への転換だ。
もう少し具体的には、「流域」という単位で考えると分かりやすいかもしれない。国土交通省が管理するだけでも、日本には2万以上の河川がある。それぞれの流域で、河川氾濫や集中豪雨による浸水リスクが高まっている。そうしたリスクに向き合いながら、どこに住み、どのように土地利用をしていくのか。流域単位での調和を考える必要がある。
この「森・里・川・海・流域」という発想と、「地域循環共生圏」というビジョンを組み合わせ、さらに日本海学的な「外に開かれた視点」を重ねると、日本は単に縮小していく国ではなく、「人類のフロントランナー」として新しいモデルを世界に示す実験場になり得る。
人口は減っていくが、生活の質、文化の厚み、民度は非常に高い。日本のアニメ、食文化、デザイン、ボーカロイドなどの音楽は、今や世界中で人気だ。こうした「日本の良さ」を、ローカルな実践からグローバルに発信していく。これを「ローカル」と「グローバル」を掛け合わせた「グローカル」と呼び、その方向で取り組みを進めている。
流域の問題は、今まさに差し迫っている。一旦大雨が降れば、一瞬で浸水・氾濫するような状況が各地で起きている。気候変動が「地球沸騰」と言われるまでに進んでいる今、自然との向き合い方が強く問われている。
周:2020年東京経済大学創立120周年記念シンポジウム「コロナ危機をバネに大転換」で中井さんと日本学術会議元会長の大西隆先生を迎え議論した。その時、里山の大切さについて大分話した。純粋な原始林より、自然への人間の適度な介入がもたらした里山の生態系の方がより豊かで災害にも強い。しかし里山のベースである自然集落は今日本で、急激に消えつつある。
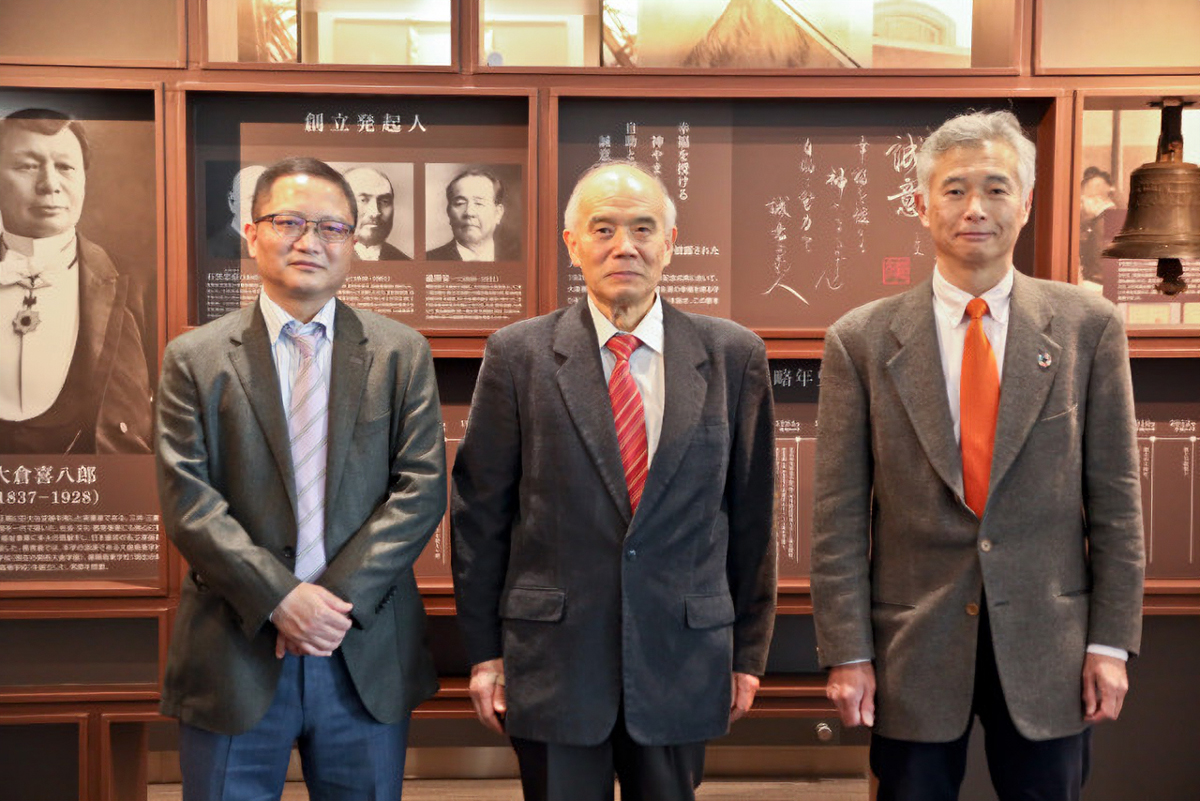
■ 日本人の自然観と祭り・建築に込められた知恵
中井:私たち日本人は、東日本大震災をはじめ、多くの自然災害を乗り越えてきた。日本列島では、3万5千年~4万年前とされる人骨も見つかっている。この間、地震、火山噴火、津波など、さまざまな自然災害が繰り返し起こったが、それらを乗り越え、自然と賢く付き合ってきた歴史がある。
日本人は、自然に対して「畏れ」と「感謝」を同時に抱きながら暮らしてきた。富士山のような美しい山の景色に感動し、そこから湧き出る水の恵みに感謝し、その水からおいしい米や酒が生まれる。その一方で、地震や噴火、台風の脅威もよく知っている。こうした感覚が、秋祭りや収穫祭、春の田植えの祭りなどを通じて、文化にビルトインされてきた。
例えば、伊勢神宮は20年に一度建て替えを行う。祇園祭は、貞観地震の後に京都で疫病が流行したことをきっかけに、「疫病退散」を祈って始まった祭りだ。八坂神社の龍穴に「邪」を封じ込めるという祈りから始まり、毎年7月17日に山鉾が巡行する形で受け継がれている。
祇園祭のような祭りは、想いを共有する場であると同時に、伝統技術を磨き続ける場でもある。毎年行われることで、技術はどんどん洗練される。また、祭りは「無礼講」の場でもあり、普段は口数の少ない人も自然と関わるようになる。ある意味、「日常の中の防災訓練」、「コミュニティの結束の場」としての機能も果たしている。
こうした自然との向き合い方、祭りや行事に込められた知恵を、現代にどう活かすか。日本人はそのポテンシャルを十分に持っている民族だと思う。
法隆寺や奈良・京都の仏教寺院の建築も、本来はインドや中国を経由して伝わってきたものだが、日本に来てから独自に磨き上げられ、最も美しい形で残っている。現代的な例でいえば、カレーライスやラーメンもそうだ。インドの人に日本のカレーを食べさせると「これはカレーじゃない」と言うが、それは日本が独自にアレンジし、別の料理に昇華させてきたからだ。ラーメンも、中国から伝わった麺料理が、日本各地で多様なスタイルに発展し、世界的にも評価される存在になった。
これは、何でも工夫し、発酵させる「醤油漬け文化」とでも言えるかもしれない。外から来たものを日本流に磨き上げる力が、日本にはある。その力を自覚し、世界に向けて発信していきたいという想いがある。

■ 「三千年の未来」と日本文明の「続ける力」
中井:私は今、「三千年の未来会議」という団体にも関わっている。役人を辞めた後、同時期に事務次官を務めた4人や、テレビ局の代表取締役、民間の人たちと一緒に、長期的な「三千年」というスケールで未来を考えることを試みている。
三千年先の未来を考えるとは、「続ける力」を持つことだ。細胞が常に生まれ変わりながら全体として生命が続くように、社会や文明も変化しながら存在し続ける。それを、良い形で持続させていく力が日本文明にはある――私はそう考えている。
奈良や京都の仏教寺院、法隆寺など、1500年近く立ち続けている建物がある。日本に入ってきた思想や文化が、自然との付き合い方と結びつき、長い時間軸で継承されている。そこには、地震や津波、火山噴火といった荒々しい自然への畏れと、富士山から湧き出る水や豊かな海の恵みへの感謝が、同時に織り込まれている。
秩父夜祭のような秋祭りは、水の恵みへの感謝の収穫祭でもある。祇園祭のような祭りがユネスコの世界無形文化遺産となり、その様式が日本各地の山車祭りにも広がっている。日本には伝統を維持しながら発展してきた歴史がある。
日本人は、そうした自然への「畏れと感謝」を織り込みながら日本列島で暮らしてきた、多様な出自を持つ人々の集まりだ。「八百万の神」という感覚があり、クリスマスでキリスト教的な顔をし、除夜の鐘を聞き、元旦には神社に参拝し、バレンタインも楽しむ。あらゆる宗教や文化を自然に受け入れる。
それを単純に「無宗教」と呼ぶのは正確ではなく、むしろ、多様な自然観や文化を包み込んできた“包容力”だと私は思う。人類が千年後も地球で生きているとすれば、最終的にはこのような感覚に行き着くだろう。今のイスラエルとハマスのような紛争を見ても、本来、人間の身体と同じように、どこか一つの源から分かれた細胞であり、「個性は違っても根っこは同じだ」というところに立ち戻らなければならないはずだ。
日本海学もまた、その一つの流れの中に位置づけられるべきだと思う。

■ 富山の雪山から生まれた政策転換
周:中井さんが話してくれた「日本海学」「地域循環共生圏」「三千年の未来」という三つのキーワードは、実はどれも、普通の官僚からはなかなか出てこないコンセプトだ。しかも、この三つをきちんとつなげて構想している。その発想のパワーは一体どこから出てきたのかを考えてみたい。
おそらく一つのルーツは、中井さんのご実家にあるのかもしれない。中井さんのお母様のご実家は、神社の宮司をされている。そこから来る感覚もあるのではないか。
コロナ禍の前、毎年のように中井さんに呼ばれ、お母様の故郷の群馬県上野村で一泊し、川で水浴びをしたりして楽しく過ごした。今思えば、上野村は中井さんの「原体験」だった。そこから中井さんの今の発想が育ってきたのではないかと感じる。
なぜこの話をするかというと、中国の環境政策の話とも関係しているからだ。中国は、環境政策を「生態文明」という文明論のレベルにまで引き上げた唯一の国だ。その原点は、中井さんとも関係ある。
二十年前、中井さんのご案内で私と当時中国国家発展改革委員会の五カ年計画担当局長だった楊偉民さんと一緒に富山を訪れた。富山の山に登り、雪の上に黄砂が積もっているのを一緒に眺めた。中井さんは、私たちにその光景を「見せつけた」。
その時のインパクトはとても大きかった。モンゴル高原から飛んできた黄砂が、日本海を越えて富山まで辿り着く。その光景は、「大陸と日本が、良い面でも悪い面でもつながっている」という事実を象徴していた。
黄砂がなければ日本海の豊かな生態系は成り立たない部分もある。他方、黄砂や大気汚染物質が運ばれてくることは、悪い面でもある。その両面を含んだ「近さ」が、富山の雪山の上で一気に可視化された。その時の経験が、私も今日のような話を考える際の原点になっている。
楊偉民さんもこの体験を原点にし、後に中国で生態文明政策の原型を作り上げた。
里山の話の延長線だが、新型コロナパンデミックの中で、欧米諸国と比べ日本の致死率が随分低かった。これはどんな要因なのか?このファクターXについて、たくさんの議論があった。2020年に私は東京経済大学創立120周年記念シンポジウム「コロナ危機をバネに大転換」での中井さんとの議論で、下記の仮説を立てた。
稲作的な里山は生物多様性をもたらし、ウイルスの病原菌の巨大な繁殖地にもなっている。そこで生活してきた我々の体の中に様々な免疫ができている。もちろん新型コロナウイルスの親戚の各種コロナウイルスからも沢山の免疫ができた。こうした免疫を「交差免疫」と言う。この交差免疫によって、稲作をするアジア諸国の致死率が低くなった。
日本だけではなく、アジアでは、中国はもちろん、ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ等もこの恩恵に預かった。西洋諸国と比べて、これらの国は決して医療のリソースが豊かというわけではない。しかし、揃って致死率が格段に低かった。私はこれが、稲作地域の里山の恩恵ではないかと思っている。
こうした尺度からも里山を貴重な存在として捉えるべきだ。
プロフィール
中井 徳太郎(なかい とくたろう)/日本製鉄顧問、元環境事務次官
1962年生まれ。大蔵省(当時)入省後、主計局主査などを経て、富山県庁へ出向中に日本海学の確立・普及に携わる。財務省広報室長、東京大学医科学研究所教授、金融庁監督局協同組織金融室長、財務省理財局計画官、財務省主計局主計官(農林水産省担当)、環境省総合環境政策局総務課長、環境省大臣官房会計課長、環境省大臣官房環境政策官兼秘書課長、環境省大臣官房審議官、環境省廃棄物・リサイクル対策部長、総合環境政策統括官、環境事務次官を経て、2022年より日本製鉄顧問。
