
■ 編集ノート:東京経済大学は2024年11月30日、国際シンポジウム「グリーントランスフォーメーションにかける産業の未来」を開催した。福川伸次元通商産業事務次官、鑓水洋環境事務次官、岡本英男東京経済大学学長、楊偉民中国第十三回全国政治協商会議経済委員会副主任、中井徳太郎元環境事務次官、南川秀樹元環境事務次官、邱暁華中国統計局元局長、徐林中米グリーンファンド会長、田中琢二IMF元日本代表理事、周其仁北京大学教授、索継栓中国科学院ホールディングス元会長、岩本敏男NTTデータグループ元社長、石見浩一エレコム社長、小手川大助IMF元日本代表理事、周牧之東京経済大学教授、尾崎寛直東京経済大学教授をはじめ産学官のオピニオンリーダー16人が登壇し、日中両国のGX政策そしてイノベーションへの努力などについて議論し、未来に向けた提言を行った。索継栓氏はビデオでセッション2「GXが拓くイノベーションインパクト」のパネリストを務めた。
私は中国科学院の索継栓です。仕事の都合により本日の会議に直接参加できず、大変残念です。ビデオを通じて皆さまと交流し、学べることを光栄に存じます。
今回の会議テーマはGX、中国語でいう「双碳(カーボンピークアウト、カーボンニュートラル)」です。これは世界が共通して関心を持つテーマで、「双碳」は中国政府が打ち出した地球規模の気候変動に対応する重要な取り組みです。
■ イノベーションでGXと低炭素発展に貢献
「双碳」の実現は、エネルギー転換、低炭素発展を促進し、経済の高品質で持続可能な発展のための重要な手段です。今後の発展理念と生態文明建設への中国の決意を表し、国際社会への責任ある大国としての姿勢を示すものです。
中国科学院は、中国の科学技術戦略の主幹として、GXと低炭素発展を推進するため数々の措置をとり、一定の成果を上げてきました。
「双碳」戦略を実施するため、イノベーションに支えられる行動計画を発表しました。ビックイノベーションの突破にフォーカスし、特に0から1へのイノベーション、すなわち革新的な基盤技術の突破に注力しています。企業と研究機関との協力で、基礎研究から重要技術の突破、そして総合的な実証まで一体化した発展システムを築いています。こうした行動計画のもとで、中国科学院は、化石エネルギーのクリーン化、再生可能エネルギーの核心技術、先進的な原子力システム、気候変動対策、汚染防止と総合的環境管理など、多くの分野で世界的にもオリジナルな成果を挙げました。沢山の重要な実証プロジェクトを実施し、数多くのイノベイティブスタートアップ企業も育成しています。
中国は「石炭が豊富、石油が不足、天然ガスが少ない」というエネルギー構造を持っています。毎年5億トンを超える石油を輸入する一方で、石炭資源が化石燃料全体の90%以上を占めています。石炭のクリーン且つ効率的な利用は、GXのカギとなります。これは、従来の石油を原料とする化学工業の発展経路をシフトさせる重要課題でもあります。中国科学院は石炭による合成油、オレフィン、エタノーなどの精製に関する多くの技術上の難題を克服しました。
これら技術に関しては、中国科学院山西石炭化学研究所が長年にわたる研究開発を通じて、多くの技術において、世界をリードする成果を上げました。こうした成果をもとに中科合成油公司を設立し、技術移転と応用を進めています。現在、千万トン規模の石炭による油精製工業装置を建設し、石炭資源の効率的かつクリーンな利用に有効なアプローチを獲得しました。
また、中国科学院大連化学物理研究所が、石炭によるオレフィン精製技術を数十年にわたって研究してきました。現在、この技術は内モンゴル、陝西、新疆、寧夏といった主要な石炭産地で実用化されています。すでに23基の大規模工業装置が稼働し、オレフィンの年間生産規模は年間3,000万トンを超えました。
再生可能エネルギーや蓄電技術においても、中国科学院は大きな成果を上げました。再生可能エネルギーの拡大にあたっては、蓄電技術のイノベーションが不可欠です。蓄電技術は、大規模な再生可能エネルギー発電を電力網へ接続する際の不安定性を緩和する基盤です。

中国科学院物理研究所は、蓄電分野において、長期にわたり研究を積み重ね、特にリチウム電池で顕著な成果を収めています。中国のリチウム電池産業の発展は、同研究所の研究成果に大きく支えられていると言っても過言ではありません。
2016年に衛藍新能源を設立、固体リチウム電池製品を開発し、電気自動車、ドローン、電気船舶など多くの分野に応用され、広範な将来性を持っています。例えば、衛藍新能源の固体リチウム電池を搭載した蔚来(NIO)の電気自動車は、航続距離が1000キロを超えました。また、低空経済をはじめとする新たな分野においても広い応用の可能性を秘めており、さらに蓄電分野においても大きな発展余地を有しています。
同時に、中国科学院はナトリウムイオン電池の開発に力を入れ、すでにエネルギー貯蔵産業において大規模な実証を行い、中国エネルギー貯蔵産業の発展に基盤を築いています。
中国科学院工程熱物理研究所は、圧縮空気エネルギー貯蔵分野で継続的に研究開発を行い、大きな成果を上げました。2021年と2024年には、それぞれ世界初の100メガワット級、300メガワット級の圧縮空気エネルギー貯蔵実証プロジェクトを完成させました。
さらに、中国科学院は、フロー電池、核融合などのエネルギー技術で大きな成果を上げています。
中国科学院はイノベーションを通じて、GXと低炭素発展に大きく貢献し、中国の「双碳」目標の実現と、経済社会の持続可能な発展を支えています。

■ レノボに代表される起業家精神が開花
中国科学院は、中国の戦略科学技術の主幹として、中国の科学技術進歩を推進し、高水準の科学技術自立自強を実現する重要な使命を担っています。特に起業家精神を発揮し、イノベイティブなスタートアップ企業を奨励するために、一連の取り組みを進めてきました。
まず中国科学院の投資企業については、中国科学院の研究成果の市場化、産業化という重大な使命を担っており、新たな生産力を育成する重要な「イノベーションの発信拠点」として、また産学研融合を推進する重要な「インキュベーション拠点」としての役割を果たしています。これら企業は、新興産業に焦点を当て、重要なコア技術分野での研究開発に取り組んでいます。そのことによって、中国の経済社会発展を支える科学技術基盤を提供しています。
中国科学院が出資する企業は1900社を超え、その多くはAI、半導体、ソフトウェア、環境保護などの分野に集中しています。現時点で、そのうち52社が上場しています。これら企業はそれぞれの分野で業界をリードする存在になりつつあります。中国科学院の成果を基盤として設立された企業は、技術を改良・高度化するため、科学院との連携を緊密に保っています。中国科学院高能物理研究所が2021年、国科控股と共同で設立した企業国科中子が一つの好例です。同社は加速器を用いたホウ素中性子捕捉療法(BNCT)の成果を産業化しました。
2015年の「科学技術成果転化促進法」の改正が研究者の起業意欲を大いに喚起し、企業と研究機関との人材交流を促進しました。それ以降、中国科学院の直接投資で555社の企業を設立し、そのうち90%が科学技術成果の産業化を目的としたものです。
起業を促す制度保障、資金支援、人材育成などの政策も打ち出しました。まず人事や評価制度に関する政策を策定し、研究者が科学技術成果の産業化に積極的に参加できるよう奨励し、その権益を保障します。資金支援の面では、科学技術成果の産業化を促す行動計画を立ち上げ、重要な科学技術成果の実用化を後押しします。さらに人材育成と交流の面では、大学や企業と協力し、科学技術産業化の専門人材を育成、各種交流活動を行い、企業と研究機関との交流・協力を強化し、イノベーション企業に人材的支えを提供しています。

皆さんもよくご存じのレノボグループ(Lenovo:聯想)は、実は中国科学院から生まれた企業です。1984年、柳伝志氏は中国科学院計算所の研究者10人と共に、わずか20万元の設立資金で、聯想の前身となる「中科院計算所新技術発展公司」を創立しました。創業初期、聯想は主にIBM、HP、SUN などの海外ブランドの販売代理を手掛けました。当時の中国産業はまだ非常に遅れていたため、聯想は積極的に事業を模索しました。同時に、研究開発を強化し、独自に「聯想式漢字カード」を開発、英語のオペレーティングシステムの中国語翻訳に成功しました。これが聯想発展の基盤となりました。
聯想は2004年、 IBMのパーソナルコンピュータ事業を買収し、本格的に国際化の道を歩み始めました。IBMのPC事業は世界的に大きな影響力を持っていたからです。当時、零細企業聯想が大企業IBMを飲み込んだとして大きな話題になりました。この買収を通じ、聯想はより広大な市場と先進的な技術を獲得し、産業システム化によって国際競争力を一層高めました。
その後、聯想は 2011年にNECのノートパソコン事業を買収し、さらに2014年にはグーグルからモトローラ・モビリティを買収しました。そして2017年には富士通の完全子会社FCCLの株式51%を取得しました。聯想は一連の国際的な買収を通じて、グローバルな経営体制を整え、世界のPC市場でチャンピオンとなりました。聯想は、国際市場を積極的に開拓し、自ら挑戦し続ける、いまや中国企業の代表的存在となりました。
レノボグループの発展は、まさに起業精神に満ちた奮闘の歴史です。また中国科学院の成果の産業化、そして国際化への一つの典型的な事例です。これらの企業は、中国のイノベイティブなスタートアップに貴重な経験を提供し、中国の科学技術分野に大きく貢献しました。
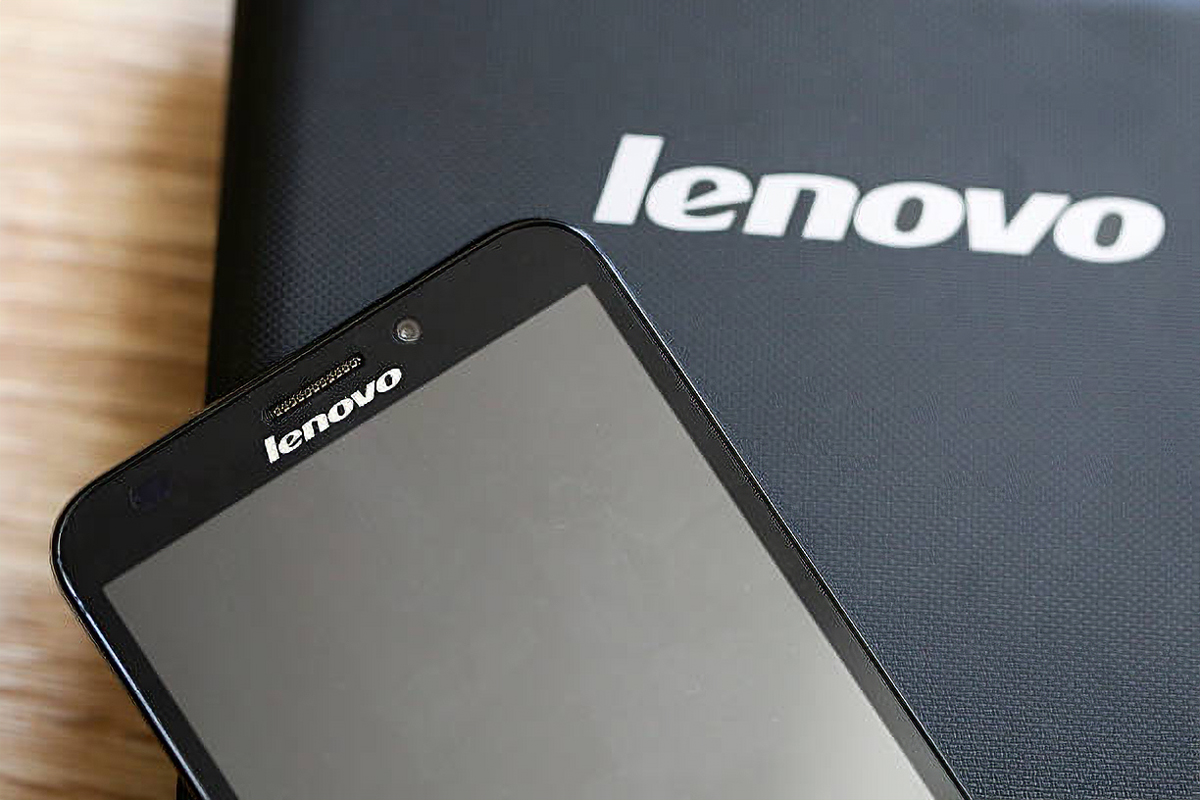
■ 日中技術交流に更なる可能性拡げるGX
私は、日中両国が科学技術分野において、広範な協力基盤があると確信しています。日中両国は低炭素・GXに向けて共通の目標とニーズを有し、幅広い共通利益と協力の余地を持っています。
石油や天然ガスといった化石エネルギーは、その埋蔵量の有限性、地理的依存性、分布の不均衡性から、強い地政学的属性を帯びています。日中両国はいずれも化石エネルギーの対外依存度が高く、輸入先が集中しているため、資源獲得をめぐる競争は不信感やエネルギー安全保障の不安を招きやすい状況にあります。それに対して、風力、太陽光、グリーン水素、原子力といったクリーンエネルギーは、その供給力がイノベーションに依存し、気候変動緩和とエネルギー安全保障の両立を支える柱です。したがってGX分野は、今後さらに両国の産業構造やエネルギー構造に大きな変化をもたらし、相互補完と相互依存を一層強め、技術交流と協力に可能性を拡げるでしょう。GX分野における協力は、日中両国の共通の利益に合致しています。
中国は広大な市場を有し、再生可能エネルギー設備、省エネ技術、二酸化炭素回収・貯留(CCS)など日本の技術に大きなマーケットを提供できます。中国における社会実装は日本企業に豊富な技術応用シナリオや実証機会を提供し、技術の絶え間ない改善と高度化に寄与します。

水素エネルギーを例に挙げると、日本はいち早く同分野の技術開発に取り組み、高分子電子材料、電磁力、極板などの重要技術において世界をリードしています。他方、中国は重化学工業のサプライチェーンが強く、水素エネルギーの大規模産業化において優位性を持っています。中国政府も現在、水素利用を強力に支援し、大規模な水素利用に必要な条件を備えています。水素産業の発展で、日中両国のカーボンニュートラル目標の達成に大きく寄与するでしょう。
中国が新たな発展段階に入るにつれて、科学技術分野における日中協力の可能性は更に拡がります。産業協力で両国はそれぞれ強みを持ち、相互補完性も高いです。日本はマテリアルサイエンス、特に高性能複合素材や特殊金属素材の分野で顕著な優位性を持ち、さらに高精度測定機器、光学機器、産業用ロボットなどの先端装備製造においても豊富な蓄積があります。また、省エネ・環境保護技術、エネルギー管理や資源循環利用の分野で豊かな経験を有しています。他方、中国は5G通信やビッグデータなど情報技術の分野で急速に発展し、新エネルギー産業化でも顕著な成果を挙げています。特に太陽光発電や風力発電の設備容量は世界最大規模となりました。EV、リチウム電池、太陽光発電製品はいまや中国の輸出における新“三種の神器”となっています。
日中両国は、幅広い共通の利益を持ち、広大な協力の可能性を持っています。両国の科学技術分野、とりわけGXでの協力は、必ずやアジアの発展、さらには人類の発展に重要な貢献を果たすものと確信しています。

プロフィール
索 继栓(さく けいせん)
中国科学院ホールディングス元会長
1991年中国科学院蘭州化学物理研究所で理学博士号を取得。蘭州化学物理研究所国家重点実験室副主任、精細石油化工中間体国家工程研究センター主任、所長補佐・副所長、中国科学院蘭州分院副院長を歴任。2014年より中国科学院ホールディングス取締役に就き、その後党委書記董事長(代表取締役)を務める。2023年より現職。その他、中国科技出版伝媒集団董事長、北京中科院ソフトウェアセンター董事長、深圳中科院知的財産投資董事長、上海碧科清潔能源技術董事長を兼任し、レノボの非執行董事・監査委員会委員も務めた。蘭州市科学技術進歩賞(二等)、甘粛省科学技術進歩賞(一等賞)を受賞。
■ シンポジウム掲載記事
■ 登壇者関連記事(登壇順)
【コラム】福川伸次:日中関係、新次元への昇華の途を探る 〜質の高い経済社会の実現と新グローバリズムの形成に向けて〜
【フォーラム】鑓水洋:地域活性化策には明確なコンセプトが求められる
【刊行によせて】楊偉民:都市のハイクオリティ発展を促す指標システム
【刊行によせて】楊偉民:全く新しい視点で中国都市の発展状況を評価する
【講演】中井徳太郎:カーボンニュートラル、循環経済、自然再生の三位一体のイノベーション—地域循環共生圏構想
【ディスカッション】中井徳太郎・大西隆・周牧之:コロナ危機を転機に
【ディスカッション】中井徳太郎・安藤晴彦・和田篤也・周牧之:省エネ・再生可能エネルギー社会への挑戦と自然資本
【フォーラム】南川秀樹:コミュニケーションの場としてのエンタメを
【コラム】邱暁華:高度成長からハイクオリティ発展へシフトする中国経済
【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅰ):誰がグローバリゼーションをスローダウンさせた?
【ディスカッション】小島明・田中琢二・周牧之(Ⅱ):ユーラシア大陸を視野に入れた米中関係
【刊行によせて】周牧之:新型コロナウイルス禍と国際大都市の行方
【論文】周牧之:二酸化炭素:急増する中国とピークアウトした日米欧
【論文】周牧之:アメリカ vs. 中国:成長と二酸化炭素排出との関係から見た異なる経済水準
